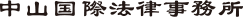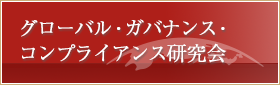2012年10月09日 ペルー・レポート ~甘美なるペルー料理~
【コラム】
南米レポート第2弾はペルーについてご報告します。ペルー労働法等の研究のため,首都リマに赴きました。
■ ペルー概要
ペルーと言えば何を連想するでしょうか。フジモリ大統領,マチュピチュ,ナスカの地上絵,日本大使公邸襲撃事件…といったところでしょうか。私もその程度の知識しか持ち合わせていませんでしたが,①アルゼンチンと大きく違って白人が少ないこと,②首都リマが観光資源に恵まれていること,③食事がすごく美味しいこと,④生活の中で感じる国の経済的未熟度など,学ぶことがとても多かったです。
■ 民族
アルゼンチンと異なり,欧米系の白人は15%しかなく,残りは先住民か先住民と欧米系の混血です。また,先住民系は背が低いのが驚きでした。身長150センチ台の男性も多いようです。私は日本でも平均より低いですが,その私でも人の頭を見下ろすような感じになります。先住民系の平均身長は,アジアのどの国よりも明らかに低いです。日本より平均で5センチ近く低いのではと思いました。
スペイン人等のラテン系民族もそれほど背は高くはありませんが,南米諸国の多くが欧米に搾取されたりした歴史も,欧米系との身長差が心理的・軍事的に関係したのではと思いました。
■ 歴史
アルゼンチンと比べると遥かに豊かで複雑な歴史を持っているようです。インカ帝国を築いた先住民文明。アメリカ大陸で「帝国」と呼ばれる歴史を有していたのはペルーくらいです。1821年にスペインから独立するまでに,16世紀のピサロの活躍などいろいろありました。現在のペルーの人口は3,000万人弱です。
■ タクシー
タクシーにはメーターがありません。乗る前に金額がいくらになるか交渉しなければなりません。これはミャンマーやロシア(場合によってはタイも)でも同様ですが,乗車拒否もされることがあるので,かなり不便というかストレスとなります。こう考えると,「メーター付きのタクシーが走っている」というのはその国の発展度合いを計る一つの尺度になるようです。
なお,ペルーではアメリカドルが通用します。アジアでアメリカドルが普通に流通しているのはミャンマーやカンボジアですが,その国の通貨が信用されていないという点でペルーも同程度の扱いを受けているようです。
■ 治安
治安はよくないようです。私の滞在中は危ない目には遭いませんでしたが,大きな家やオフィスはどこも高い塀で囲まれ,その上に有刺鉄線か防犯用の電線が引かれています。法律事務所の入り口の塀にも表札も何もなく住所番号があるだけで,外見からは法律事務所だと全く分かりません。法律事務所であることを示すと泥棒の標的になるからそうしているそうです。
訪れた法律事務所は,外観(塀の高さが約5メートル)もセキュリティも,大使館のような重々しさがありました。このような厳重な防犯状況にある街を歩いていると,肌感覚として治安が悪いことが感じられます。
■ リマ
①荘厳な歴史的建築物と②美しい海岸地帯と③古く汚い車のコントラストが印象的でした。インドのタージマハル周辺でも感じましたが,数百年昔から壮大な建築物を建造する権力や技術があるのに,現代において市井の人々がその生活において偉大な遺産を享受できていないように思えるのは,やはり搾取・苛政が続いてきたせいでしょうか。
地面はブエノスアイレスほど汚くなく,清掃・整備が行われているのだと知れます。地下鉄がないこともあるのでしょう,市内の一部はものすごい渋滞を引き起こしていました。
ただ,アスファルトの舗装技術がないからか,路面の微妙な段差が身体に振動するので,車での移動が快適とは言えません。また,車の密集地域では,インドほどではありませんが,常にクラクションがけたたましく鳴っていました。
走っている車の多くは非常に古く,例えばタイやインドネシアより古い車が多かったです。ペルーの一人当たりGDPはタイと同程度でインドネシアより高いですが,肌感覚ではペルーの方が未発展だと思いました。一人あたりGDPは一つの指標になりますが,一方で一つの指標にすぎないことを実感しました。
アルゼンチンで頻繁に目にした落書きがペルーでは少ないこと,アジア諸国にも落書きはほとんどないことからすると,落書きがヨーロッパ文化?と語られることにも合点がいきます。
■ ペルー人
傲岸な白人と純朴な先住民という図式は南米にもまだあてはまるようで,南米の人でもアルゼンチン人を嫌う人がいたりするそうです。ペルーでは入国審査や裁判所へ入る際のチェックも牧歌的な雰囲気がありましたし,先住民の血を引いた多くのペルー人に対しては,モンゴロイドに対する親しみやすさを感じました。
■ 日系人
ペルーに9万人程度(約300人に1人)いるはずですが,ほとんど見かけませんでした。ペルーでは広く東洋系を「Chino(チーノ)」と呼称し,日本人もチーノに含まれます。
■ ペルーの法制度と運用
アジア諸国にあるような投資優遇制度がありません。強い保護主義的な制度があるというわけではありませんが,日系企業からすると,インセンティブがないため投資はしにくいようです。また,役所への届け出でも人によって対応が違ったり,賄賂を払わないと対応してもらえかったりという途上国特有の問題を抱えています。そのため,ビジネスを行う際にはキーパーソンとのつながりが特に大事になってくるようです。
労働法は,アルゼンチンとは異なり,解雇に正当事由が必要であることなど,労働者保護に傾いています。これは,労働者の中に多い先住民を保護すべきという文化的要請が背景にあるようです。アルゼンチンで,アルゼンチンに投資しようとする白人の側に立ち,使用者を保護すべく解雇に正当事由が不要であることと対照的でした。
労働裁判は,今年11月から口頭審理を行う新しいシステムに移行して裁判の迅速化を図っているようです。労働裁判所の一室(日本の弁論準備室のようなところ)で行われた裁判期日を傍聴しましたが,期日後にその裁判官が我々にペルーの労働裁判につき懇切丁寧に英語で説明してくれたのが印象的でした。
■ 貴重な友人関係
IPBAのメンバーでもあるシンガポール国立大学時代の親友の紹介で元労働大臣に逢えたり,親友の自宅に泊まらせてもらったり,ハイヤーを手配してもらったりと,大変な歓待を受けました。留学やIPBAを通じて人との貴重なつながりができることの有り難みを,改めて実感しました。
■ 自動車
リマを走っている車のうち日本車は2割程度でしたが,新車のうち日本車のシェアは4割だそうです。アルゼンチン同様,高級外車はほとんど走っていません。マーケットが大きくないことと輸入関税の低さから,自動車をはじめとする製造業の進出は難しいという意見もあるようです。
交通量の多いところでは,排気ガスの匂いが漂ってきます。走行車両の排気設備が日本と比べ悪いのでしょう,日本よりかなり空気が汚染されていることが分かります。なお,タクシーはほとんど空調設備がないようで,窓を開けて走っています。
■ グルメの国
ペルーは自他ともに認めるグルメの国です。肉料理の多いアルゼンチンと違い魚料理が豊富で,味付けも脂っぽくなく,日本人の舌に合っています。日本に導入したら流行るだろうという料理がいくつもありました。
調べると,ペルーの漁獲量は中国に次いで世界第2位。また,ポテト(じゃがいも)の原産地はペルーだそうで,ペルーには2,000種類以上のポテトがあるそうです。
■ リゾート地としてのリマ
リマの中心から太平洋岸まで数キロのところに,ラルコ・マールという商業施設があります。断崖の下に美しい太平洋を臨む景観は,世界でも有数と言えるほどで,リゾート地としての魅力を有しています。
東京の都心から太平洋を臨むビーチの開放的な気分を味わうには1時間以上かかりますが,リマではそれが目と鼻の先にあります。ペルーといえばマチュピチュばかりが語られますが,リマだけでも観光資源が豊富な魅力のある街だと知りました。
以上
2012年10月09日 アルゼンチン・レポート ~南米のパリは汚かった~
【コラム】
ラテンアメリカ労働法の研究目的でアルゼンチンとペルーに行って参りました。南米レポート第一弾としてまずはアルゼンチン事情をお伝えします。
■ アルゼンチン
豊富な資源に支えられ1929年には世界で5本の指に入る大国でしたが,2002年に財政破綻し,一時は失業率が20%を超えることもありました。最近は財政的に持ち直しているようであり,街の一部を見ただけでしたが,失業者が溢れているような光景はありませんでした。
ただ,至る所でゴミが散らかっているのが驚きでした。財政悪化のせいですが,これは後述します。また,インフレが激しいためか貨幣が信頼されていないようで,アルゼンチンペソをペルーでペルー通貨のソルに換えようとしましたが断られました。
■ アルゼンチン人
いわゆる「南米」的な,先住民の血が明らかに混じっていると思われる顔(例えば,マラドーナのような顔)はほとんどなく,メッシのようにいかにも「白人」という風貌がほとんどです。他の南米諸国と大きく異なり,9割方はスペイン系・イタリア系の移民で,白人国家とも言われています。
国民に一番人気があるのは,エビータの愛称で知られるエバ・ペロン(33歳で夭折した,ペロン大統領夫人)のようです。至る所にエビータの肖像・写真がありましたが,マラドーナやチェ・ゲバラの写真は見かけませんでした。
観光客が集まる場所であっても,日曜日には多くの店が営業を休んでいました。営業利益よりも休暇を優先する国民性か,教会での礼拝が理由なのか分かりませんが,これもラテン系ゆえかと思いました。
■ 日系人
日系人は2万人強いるようですが,ほとんど見かけませんでした。また,日本人観光者も見かけませんでしたし,アジア系の風貌自体が希有でした。黒人もほとんどいません。日本食レストランも多くなく,街で日本語は見かけません。
中国人と見分けがつかないからか,「ニーハオ」と話しかけられることもありました。先月赴いたサンクトペテルブルクで白人の多さとアジア人の少なさを強く感じましたが,ブエノスアイレスでも同様の印象を受けました。
■ ブエノスアイレス
首都ブエノスアイレスは,都市圏人口約1,300万人の大都市。100メートル四方の正方形ブロックが街区を構成し,50メートルほどの高さ制限もあるようで,整然とした街並みは「南米のパリ」とも言われています。
ただ,パリと異なり至る所に落書きが溢れ,路面もでこぼこでとても歩きづらく,ゴミも多く散らかっており,お世辞にも綺麗な街とは言えません。
地球の真裏にあるため,時差は12時間で日本とちょうど半日違い。冬から春になる時期でしたが,日中はTシャツ1枚で動ける陽気な日もありました。
19世紀初頭の独立以降に発展したため歴史はさほど古いとは言えませんが,それでも100年規模の歴史を誇る建造物は多かったです。木造建築が多く空襲や震災で歴史的建築の多くを失った日本に比べると羨ましい思いがします。
独立記念日にちなむ7月9日大通りは世界最長の幅員を誇り,片道10車線,双方向で20車線です。日本車の数は1割にも満たないようです。他の高級外車もほとんどみかけませんでした。
地下鉄が6本も走っており,そのうち1本は100年以上前に敷設されたもので,20世紀初頭のアルゼンチンの繁栄を物語っています。これは日本最古の銀座線より古く,銀座線敷設前に日本から視察使節が来たそうです。
■ 散乱するゴミ
ブエノスアイレスの落書きや落ちているゴミの多さは,私がこれまで訪れたアジア・アフリカ・欧州諸国の中でも群を抜いていました。経済事情が悪く清掃員を働かせることができないためだそうです。これでは南米のパリも台無しだと思いました。
■ スペイン語
ほとんど英語は通じず,スペイン語しか通じません。私が外国人(観光客)だと一目で分かるであろうに,当然のようにスペイン語で話しかけてきます。スペイン語と英語の単語には共通するものもありますが,共通しないものはある程度勉強しないと全く分かりません。
例えば,お土産屋で値段を聞いても「シンクエンタ(50ペソの意)」などと言われるし,男性用トイレの表示も文字で「Caballeros(男性)」「H(hombre=男性の略。女性はM=mujer)」と書いてあるだけのところもあり,全くスペイン語を知らないとかなり苦労します。また,スペイン語圏の英語話者は,10時15分を”a quarter past ten”と表現する人が多いようです。
■ 弁護士事務所訪問
300人以上の弁護士を擁するアルゼンチン最大の法律事務所に勤める,IPBAの友人弁護士事務所を訪問しました。アルゼンチン法に関する貴重な情報を入手することができ,IPBAのつながりは改めてありがたいと思いました。
瀟洒なオフィスでしたが,「この事務所には何人の弁護士がいますか」と受付のお姉さんに訊いたところ,「Muchas(たくさん)」という回答が笑顔で返ってきたのがラテン的だと思いました。
■ アルゼンチン労働法
シンガポールやアメリカの多くの州と同様,解雇には正当事由が不要です。国内投資と移民を促進するため使用者寄りの労働法を用意しています。これは,先住民の血を引いた労働者が多いペルーで,労働者保護のために解雇に正当事由が必要であるのと対照的でした。
使用者を保護する(アルゼンチン)のか労働者を保護する(ペルー)のかは,先住民労働者を保護すべき要請がどれだけ多いかという文化的・社会的背景が影響しているようです。これはペルーに関するレポートで後述します。
■ JETRO訪問
ブエノスアイレスにあるJETRO事務所はサンパウロ事務所の支局という扱いにすぎず,サービスオフィスの一角に10畳くらいの一室を借りているだけで,アルゼンチンの日系企業に関する情報は得られませんでした。
例えば日系企業が多いバンコクのJETROオフィスには図書室がありタイの法律情報が得られますが,さすがに地球の裏だと対日貿易の影響力は小さいのだと改めて思いました。支局に格下げされたのは事業仕分けの影響だそうです。
■ 最高裁判所見学
荘重な建物ですが,下級裁判所の機能を兼ねているからか,誰でも自由に出入りできるカジュアルな雰囲気で,床には巻かれたビラが散乱していました。極めて静粛で緊張感のある日本の最高裁判所とは大違いでした。
■ 充実した法律書籍
最高裁判所近くの法律専門書を扱う書店でアルゼンチン法に関する文献を探したところ,学説に重きを置くシビルローの国だからか,多くの本が出版されていることが印象的でした。この点は,判例を重視して学説を重視しないコモンローの国シンガポールと大きく違うようでした(シンガポールの歴史が浅いということもあるでしょうが)。
■ 食事
牧場に恵まれているからか,牛肉が有名です。1キロ弱のステーキが出てきたときには驚きました。また,ぶどうも採れるのでワインでも有名です。
以上
2012年09月29日 タイ・レポート 2 ~タイの労働法事情~
【コラム】
先日,第一東京弁護士会の労働法制委員会の外国法部会で,タイ労働法に関する講師として招かれる機会がありました。同部会で話したタイ労働法の特徴を簡単に紹介します。
1 解雇に対する厚い保護
日本と同様,解雇には正当事由が必要です。以下に述べるように,労働裁判所での無料かつ口頭での提訴が許されていることからも,労務紛争を未然に防止するためには安易な解雇を回避しなければなりません。
また,日本と異なり,解雇の際には法定の解雇手当を支払う必要があります。おおよそ1年勤務につき1か月分の給料相当額が解雇手当として法定されています。なお,便宜上一般の呼称に従って「解雇手当」という用語を使用していますが,解雇の場合のみならず,定年の場合など会社都合で労働者を退職させるときに広くこの「解雇手当」の支払義務が発生します。その意味では,解雇手当というよりは「離職手当」という用語の方が日本語の本義に近いことになります(本稿では一般の慣用に従って解雇手当という用語を使用しています)。
2 厳格な労働協議の手続
労働協議をする際に,相手方に通知書を事前に交付したり,労使協議が不調の場合は労働争議調停官による調停が必須であったりするなど,厳格な手続が定められています。労働組合も他国と比べると脆弱ですし,敬虔な仏教徒が多く使用者と対立関係になることを好まないためか,他のアジア諸国に比べてストライキは少ないといえます。
3 慢性的な人材不足
タイの失業率は2〜3%と低く,また,大卒者の割合が低いことなどから優秀な人材が限られているため,アジアの中でも最も人材確保が問題になっています。
また,タイ人は,日本のように終身雇用に近い価値観を持っていることはほとんどないため,少しでも給料が高い企業に簡単に転職(ジョブ・ホッピング)してしまいます。そのため離職率が一般に日本より高く,労働者に様々なインセンティブを与えて容易に退社されないような工夫をすることが重要です。
4 最低賃金上昇
インラック新政権の公約に基づき,2012年4月から,最低賃金が上昇しました。場所によっては40%上昇したところもあり,その余波を受けて日系企業の賃金も平均で10数%上昇したようです。
5 労働裁判所
労働問題については,労働裁判所という特別裁判所が用意されており,労働者が無料かつ口頭で提訴することができます。弁護士費用や訴状作成の負担がないので,労働者からの提訴のハードルが日本の裁判所に比べて低いことに留意する必要があります。
6 タイ特有の労務対策
一般的に,タイ人はプライドが高く体面・面子を大事にすると言われています。そのため,人前で労働者を叱責することは御法度とされています。その他,タイ人の笑顔の下に隠された真意を知ることが大切だったり,家族を大切にするタイ人の価値観に配慮する必要があったりするなど,日本とは異なる対処が必要になります。
以上
2012年09月09 日 ロシア・レポート ~領土問題と日露ビジネス~
【コラム】
先日,IPBA(環太平洋法曹協会)のAPEC(アジア太平洋経済協力)委員会でロシアのサンクトペテルブルクに出張して参りましたので,ロシア事情などをご報告いたします。
■ 訪問目的
先日ロシアのウラジオストックでAPECが開催されましたが,それに先立ち,APECの中小企業部会(Small and Medium Enterprises Working Group Meeting)にIPBA代表として出席しました。IPBAとAPECは,対象とする地域(アジア太平洋地域)が重なることもあり,2年前から友好協定を結んでいます。
その友好関係をIPBAとして今後どのように活かしていくかを模索すべく,各国代表合計数十人が出席する部会の末席を汚させてもらうことになりました。APECの会議に出席するのは初めてでしたが,IPBAとは異なる議事進行などが勉強になりました。
■ サンクトペテルブルクという街
サンクトペテルブルクは,ソ連時代はレニングラードと呼ばれ,世界最北の100万都市です。200年ほど帝政ロシアの首都でした。高緯度のため,夏なので朝4時から夜24時まで明るかったです(気温は20~25℃程度)。逆に,冬は朝10時から昼3時くらいまでしか陽が出ないようです。
最後の半日は観光に充て,エルミタージュ美術館や血の上の救世主教会など,古都ゆえの由緒ある建築物等を多く堪能しました。他の多くの欧州の都市と同様,建築制限により高さ約30メートル以上のビルがほとんどなく,しかも高さが揃っていため,街並みがパリのように美しいことが強く印象に残っています。
日本では,京都で高さ制限がありますが場所によって異なるため高さが揃っているということはなく,銀座も屋上広告を含めると66メートルなので人間の感覚からするとだいぶ高く,やはり高さが揃っていません。欧州のような石造りの街と,日本のような木造建築が多い(多かった)国では市街地の景観を単純に比較できませんが,景観保護のために政治が強く機能してきたであろうことを感じました。
■ ロシア人
印象に残ったことは,街ですれ違う人の約99%がコーカソイドである(つまり,アジア人や黒人をほとんどみかけない)ことです。このような街は世界的に見ても珍しいのではと思いました。
抱いていた先入観と異なり,ヒョードルやシャラポワのような,すれ違っただけで「ごめんなさい」と言いたくなるような肉体的威圧感のある人はさほど多くなく(100人に1人くらいでした),自分より小さいロシア女性などに逢うと,ロシア人に対する親近感が湧いてきました。やはり百聞は一見に如かずということでしょうか。
また,東南アジアでよく見かける「追従的」笑み(例えば,タクシー運転手がおつりを払わないときに作る「勘弁してよ,旦那」的な笑み)を見かけません。
社会主義体制に慣れてサービス精神が発達していないからか,愛想笑いもなく,テーブルに伝票を叩き付けるようにして置いていくレストランの店員。ああここはアジアではないのだなと改めて感じました。
■ ビジネス事情
ロシア人弁護士と一時間ほど日系企業の投資状況などについて話し合いました。聞けば,医療や自動車産業が未発達である点など,ロシアに日系企業が食い込む余地は十分大きいようです。
しかしながら,日系企業の進出は芳しくありません(ロシア全体の登録在留邦人は2,000人強で,シンガポールの10分の1,タイの20分の1です)。その理由を尋ねると,一言「Perception」。領土問題に触れた後の文脈で語られた言葉なので,戦争と領土問題の影響は日露ビジネスにも色濃く影を落としていることを知りました。
実際,ロシアは我々の紛れもない「隣国」ですが,我々は韓国ほどに親近感を抱いているとは言えません。それは人種が異なることもあるでしょうが,やはり長年の領土問題が影響していると言えるでしょう。
なお,ロシア人は案外親日的で,サンクトペテルブルクで最も人気のある料理は,スシだそうです。戦争を知らない世代(つまりは,互いに偏見を持たない世代)が増えることで,日露ビジネスも今後より活性化するだろうという意見も聞きました。
ウラジオストックでAPECが開催された理由の一つに,ロシア側の極東開発目的があると言われています。日系企業がアジアを中心に進出する中で,今後ロシアへどれくらい進出するようになるか,注目したいところです。
なお,ロシア人弁護士が「ロシアはアジアに位置する」と定義づけていましたが,実際調べてみると,ロシアの特にウラル山脈以東は「北アジア」に分類されるようです。日本的な感覚では「アジア」という語にロシアを含めることは多くないように思いますが,この辺の感覚にも我々のロシアに対する距離感が反映しているようです。
■ 弁護士事情
弁護士はアドヴォカートと呼ばれますが,それとは別にユリストという日常用語があり,これは主に弁護士資格を有さずに代理人業務を行う者のことを指します。
日本では民事でも代理業務は基本的に資格を有する弁護士しか行えませんが,ロシアでは民事事件では弁護士資格を有さないユリストも代理人となることができます。
訪れた弁護士事務所の会議室の内装が,宮殿に用いられる柱をモチーフとしていたのが印象的で,当然ではありますがロシア的美的感覚が日本人と異なることを感じました。
以 上
※ 日本IPBAの会ホームページにも記事を載せております。2012年06月30日 ミャンマー・レポート 4
【コラム】
中山達樹です。先日ミャンマー投資に関するセミナーを行い,お蔭様で好評をいただくことができました。今回は,ミャンマー投資のメリットとデメリット,そして最新の法改正情報等をお送りします。
■ ミャンマー投資のメリット
主に以下の7つを挙げることができます。
① 未開拓な消費市場
② 安価で豊富な労働力
③ 地理的・地政学的重要性
④ 良好な対日感情
⑤ 最近の民主化路線
⑥ 豊富な天然資源
⑦ 対日特恵関税の適用
以上のようなメリットがあるため,「東南アジア最後のフロンティア」「ポスト・ベトナム」として,新・新興国の雄と謂われています。ASEANの途上国のうち日系企業の進出が進んでいないミャンマーとラオスとカンボジアの頭文字を取って「MLC」と呼称する動きも現れました。
以下,いくつかメリットを掘り下げてご説明いたします。
① 未開拓消費市場
人口約6,200万人で国土面積は日本の1.8倍ですが,長い軍政や社会主義体制のため,50年近く事実上の鎖国状態にありました。そのため様々な点で近代化に遅れを取っています。
一人当たりGDPは832USドルで,日本の55分の1=江戸時代並みです。そのため伸びしろがとても大きく,期待されています。
昨年3月に民政に復帰してから投資熱に火が点き,今年4月の補欠選挙でアウンサンスーチー率いる政党が勝利してから,欧米が経済制裁を停止して,さらに投資熱が盛り上がっている状況です。隣国タイや中韓はすでにミャンマーへ進出していますが,日系はこれからという段階です。
これまでミャンマーは中国寄りの政策を取ってきましたが,アメリカはオバマ政権になってから制裁一辺倒ではなく柔軟に制裁緩和・進出の動きを見せており,米中という二大大国の覇権抗争の舞台になる様相を呈しています。米中の政治的駆け引きからも目が離せないところです。
② 安価で豊富な労働力
一般工(ワーカー)の給料は月額6,000円程度,年間負担総額でも9万円程度であり,東南アジアでは最も安価な労働力です。これはベトナムの2分の1で,タイの4分の1くらいです。
また,人口約6,200万人のうち24歳以下が44%であり(国民の平均年齢は27歳。ちなみに日本は45歳),出生率も高いので,これから若い労働力がどんどん供給されます。さらに,9割が仏教徒であり敬虔な信者も多く,識字率も約9割と高いことから,日系企業としても扱いやすいといわれています。かつてイギリスの植民地であったことから,特に都市部オフィスワーカーは,英語が話せるという点も魅力です。
③ 地理的・地政学的重要性
隣接5か国(インド,バングラデシュ,中国,ラオス,タイ)の人口はなんと約26億人で,世界人口の4割を占めます。
南北東西回廊(メコン回廊)の開発により,交通の要衝としてさらに重要性は高まっています。
バンコクとヤンゴン(やダウェイ港)を横断する陸路が開発されれば(商業化にはあと数年かかるようです),マラッカ海峡を経ずに中印を結ぶことができ,「陸のASEAN」の経済はより活発化することでしょう。
④ 良好な対日感情
かつての侵略という歴史にかかわらず,東南アジアでは一般に対日感情は良好といえますが,ミャンマーもその例外ではありません。その背景としては以下の要素が挙げられます。
・戦後賠償やODAで示した豊富な資金力
・高い技術力
・同じ仏教国という親近感
・対中韓警戒感(他国にはない日本独自の信頼性)
・アウンサン将軍の滞日経験や日本軍がビルマの独立に寄与したという歴史的つながり
⑤ 最近の民主化路線
2003年の「民主化ロードマップ」発表以後,アウンサンスーチーの軟禁延長など紆余曲折はありますが,基本的に民主化路線を歩んでいます。
現政権も未だ軍政の残滓はあるので完全に安心はできませんが,2014年にはミャンマーがASEAN議長国に就任することが決定しており,2015年にはASEAN経済共同体が設立するとも謂われていますので,ミャンマーの民主化路線は基本的に揺るがないと思われます。
■ ミャンマー投資のデメリット
主に以下の5つを挙げることができます。
① 未熟かつ不透明な法制度
② 政治リスク
③ 未整備なインフラ
④ 対日輸送の物流コスト
⑤ 厳しい送金規制
以下,掘り下げてご説明します。
① 未熟な法制度
びっくりするのは,労働法や商標法のような基本法が存在しないということです。特許法や意匠法もないので知的財産権の保護が不十分であることはかつてご紹介しました。労働法や上記知財関連法は現在改正作業中であり,その他,最低賃金法や社会保険法も今年2012年中に制定予定です。
また,汚職もはびこっているので法実務全般に予測可能性は低いといえます。主要法は現在制定作業中ですので,早急の法整備が待たれるところですが,法律が整ってから進出するのでは先駆者利益が確保できないので,悩ましいところではあります。
② 政治リスク
民政に移行したとはいえ,国会議員の4分の1は制度上軍人が就任するものとされ,実際,国会議員の大半は元軍人や現役軍人が占めています。しかも,現行憲法改正には国会議員の4分の3以上の賛成が必要であることから,軍人が賛成しなければ憲法改正も事実上不可能です。
ただ,2011年から政治集会やデモ行進が可能になり,インターネット規制も緩和されました(それまではYouTubeも閲覧できませんでした)。遮断されていた情報が開かれることで,民主化の流れは止めることができないように思われます。今後も注視したいところです。
なお,ミャンマーには少数民族が135もあり,「アジアのユーゴスラビア」とも言われています。少数民族の中には武装化して政府と停戦合意などの緊張状態にある部族もあり,特に国境周辺は治安が危険視されています。タイとの国境あたりは麻薬の製造拠点「Golden Triangle」としても有名です。
③ 未整備なインフラ
電力供給能力は上昇していますが,国全体の発電能力が沖縄電力並みの段階にあり,まだまだ電力の供給に不安があります。ヤンゴンでも1日3~4回は停電します。そのため,企業・工場では自家発電設備が不可欠であり,この設備維持コストが結構掛かります。
道路の舗装率も40%足らず(二車線は10%)であり,現実的な進出対象は工業団地だけと考えられていますが,30弱の工業団地のうち,使用に耐え得るのはヤンゴン北部のミンガラドン工業団地のみとも言われます。そのミンガラドン工業団地の入居率は今年初頭に100%に到達してしまい,日系企業が安心して進出できる具体的な地名が挙がりにくいところです。
④ 対日輸送の物流コスト
ヤンゴンとバンコクを結ぶ陸路はまだ開発中であり,幅員が狭いなど道路状況劣悪で通行規制等もあり,まだ商業化には至っていません。
そのため現状はマラッカ海峡経由の海路が現実的な選択肢ですが,対日輸送に3~4週間掛かります。
⑤ 厳しい送金規制
貿易取引以外の収入や配当の海外送金は,一定額以上は中央銀行の外貨管理部の許可が必要であり,これまでは2行の国営銀行のみを通して行われていました。昨年から4行の民間銀行でも海外送金は可能になりましたが,まだスムーズに行われていないという情報もあります。
■ その他最新の法改正情報
法人税率は今年4月から30%ではなく25%に減額されました。
また,外国投資法に基づかず,会社法に基づき会社を設立する場合の最低資本金が,今年3月までは現地通貨のチャットで計算されていましたが,今年4月からは製造業等15万ドル,サービス業等5万ドルになりました。
以上です。7月27日には日本ナレッジセンターで,10月にも金融ファクシミリ新聞社でミャンマーセミナーを行います。ご興味ある方は奮ってご参加ください。
2012年06月21日 インドネシア・レポート ~日本車シェアは世界最大~
【コラム】
先日出張に赴いたインドネシアについて,簡単にレポートします。
■ 総論
約2億4,000万の人口。国民の一人あたりGDPが3,000ドルを超え,白物家電やバイクなどの耐久消費財を購入する中間層が爆発的に増加しつつあることから,安価な労働力の供給地というだけではなく,最も成長性の高いマーケットとして大いに注目を集めています。
なお,インドネシア国民の平均年齢は28歳(日本は45歳)で,出生率は2.2です。今後50年以上,人口構成の恩恵を受けて高度な経済成長が見込まれる「人口ボーナス」状態にあると考えられています。
■ 「品物損害クラーム」
インドネシアの玄関,ジャカルタの国際空港でまず目に入ってくるのが上記日本語です。これが「Baggage Claim」の日本語訳(のつもり)であること,つまり発音も意味も正確に訳せないことが,この国の何かを象徴しています。
■ 渋滞
首都ジャカルタ(人口約1,000万人,近郊を含めると2,300万人)の交通渋滞は,モスクワ,メキシコシティ,北京やサンパウロと並んで,世界 最悪と言われています。地下鉄や鉄道がないことが原因です。2016年に鉄道が敷設される予定ですが,その工事期間中はさらに渋滞が悪化することが予想さ れます。
あまりにひどい渋滞のため,一日の大半を車中で過ごすことを余儀なくされることも多く,基本的に午前に1件,午後に1件しかアポイントを入れることができません。また,雨が降ると道路はすぐ冠水し,セダンでは走れなくなるため,背の高いSUVばかりが売れています。
■ 在留日本人
インドネシアに日本人は1万人強滞在しており,シンガポールの半分,タイの5分の1程度です。治安が悪いことなどから,ほとんどが単身赴任者です。シンガポールやタイと異なり,男性でも夜の一人歩きは危険とされています。
■ 日本車
インドネシアの日本車(四輪車)のシェアは,世界最大の95%。日本でさえ日本車は93%であり,これを凌ぎます。二輪車の日本メーカーのシェアは 99%です。これだけ日本車が席捲していれば,日本に親近感を抱き,対日感情が良くなるのもうなずけます。ただ,日本車が渋滞を引き起こしていると考える と,ちょっと複雑な気分です。
■ 対日感情
JKT48に代表されるように,とても対日感情がいい国です。東南アジアはどこでも対日感情は良好ですが,あるデータによ れば,中でもインドネシアの対日感情は最もいいそうです。約350年続いたオランダの苛烈な植民地支配から解放されるのに日本軍が寄与したという考えが根 底にあるのかもしれません。
今回の出張では,日本の大衆料理店である「大戸屋」に入りましたが,ジャカルタでは高級百貨店の中の高級料理店という位置づけでした。
■ 賄賂・汚職
インドネシアといえば汚職が有名です。裁判は賄賂で左右されると言われ,信頼されていません。シンガポールのチャンギ空港よりもはるかに見劣りするジャカルタの国際空港が,チャンギ空港と同じ建設費用を掛けて建設され,その費用の多くは袖の下に消えたと言われています。
■ 宗教
世界最多のイスラム教徒を抱えています。ただ,インドネシアのイスラム教は穏健と言われ,酒を嗜む人も多いですし,女性も西洋社会と変わらない服装 をしている人が多いです。それでも,ラマダン(一か月の断食)の戒律期間中は,太陽が昇っているうちには断食をしているため,従業員の業務効率が落ちたり します。
■ 料理
正直,タイなどと比べると,あまり美味しい料理はないと思います。日本人の口に合うのはナシゴレンやミーゴレン(焼きそば),そしてサテー(ココナツ風味の甘いタレをかける焼き鳥)くらいでしょうか。
■ Facebook
Facebookの利用者数は世界第2位。勤務中に携帯をいじくる従業員が多いのが企業の悩みどころとなっています。
■ インドネシア語
公用語のインドネシア語は,時制がないなど発音も文法も簡単であり,日本人にとって最も習得しやすい外国語と言われています。実際,数か月でマスターしてしまう日本人もいます。
■ 法制度
旧オランダ植民地であったことから,シビルロー(制定法)の国といえます。家族法などの分野では,固有の慣習法Adat法が用いられています。
■ その他法制度・法実務の特徴
一般的な外資規制の他には,進出日系企業としては以下のようなインドネシア法の特徴に留意する必要があります。
(1) 会社法関連
ア 会社の人事責任者には,インドネシア人を置かないといけない
イ 特別決議要件が日本と異なること
定款変更等が投票数の3分の2以上で,解散等は4分の3以上と分かれています。
なお,アジアでは,日本(3分の2)と異なり,4分の3以上という特別決議要件を置いている国がほとんどです。
ウ 監査役(コミサリス)の設置義務があり(日本と異なり,外国では監査役は一般ではありません),その監査役に,取締役の業務一時停止という強い権限が与えられている
(2) 労働法関連
ア 労働組合が強い
イ 解雇が困難(法定の解雇手当以上の金額を支払うことが多い)
以上です。今後も適宜,諸外国の法律事情などをご紹介する予定です。
2012年06月18日 ミャンマー・レポート 3 ~法律事情~
【コラム】
ミャンマー・レポート第三弾は,ミャンマーの法律事情の概要をお届けいたします。
■ 総論
ミャンマーは,法制度もかなりプリミティブ(未発達)です。100年以上前のインド植民地時代に制定された法律をまだ使用していたり,商標等の登録が十分 に機能していなかったりすることなど,日本人の感覚からはびっくりさせられることも数多くあります。現在,急ピッチで法整備が進められ,どんどん新たな主 要法が制定されており,数か月単位で状況が大きく変わるという印象です。
■ 法制度
旧イギリス植民地であったことから,現在はコモンロー(判例法)の国といえます。ただし,契約法や不法行為法に関する成文法であるビルマ法典が存在し,その適用解釈が行われている点で,制定法に近いということができます。
■ 投資法改正
最近の最大の動きは,外国投資法が改正されることです。免税期間が3年から5年(一定の要件を満たせば8年)に伸張されたり,民間用地もリース可能になったり,リース可能期間が延長されたりするなど,進出日系企業に有利な改正が予定されています。
■ 為替相場の統一
これまでは公定レートと市場レート等が別々に用いられており,その差が100倍以上もあったため相当の混乱を招いていました。ところが,今年4月から,中 央銀行が公表する管理変動相場制(5月10日現在:1USドル=824チャット)に統一されることになりました。
■ 労働環境
ワーカー(製造業の作業員)の年間実負担額は,わずか 1,000USドル(約8万円)程度。つまり,月額では,1人6,000~7,000円で一人のワーカーを雇うことができてしまうという,東南アジアでも 最も賃金が低廉な国です。低賃金で評判のベトナムと比べても,3分の1程度しかありません。そのため,衣料や履物などの労働集約型産業で対日輸出の約7割 を占めています。今後も縫製業を中心とするミャンマー進出が進むと思われます。
■ 知的財産
商標,特許,意匠について固有の法律がなく,刑法その他の関連法によってかろうじて保護を図ろうとしている状態です。これらの知的財産権については,約 100年前に制定された著作権法とともに,現在法律を制定作業中です。興味深いのは,これらの知的財産権を登録することはできるものの,この登録によって も,他国と異なり,その知的財産権に完全な保護(例えば専用権や禁止権)を与えているとはいえないという点です。進出企業にとっては,一刻も早い関連法の 制定・施行が待たれるところです。
■ NY条約締結
ミャンマーは,世界のほとんどの国が批准しているニューヨーク条約を批准していません。そのため,他国で行われた仲裁の判断がミャンマーでは執行力 を有しないと考えられていました。ところが,今年に入ってから,ミャンマーが同条約を批准する方向であることが明らかにされました。批准されれば,他国の 仲裁判断がミャンマーでも執行できるという建前になります。これは,国際紛争の観点からは,画期的なニュースといえます。
以上,ミャンマーの法制度概要をお届けいたしました。詳細は,6月29日(金)に開催される経営調査研究会主催のセミナーでご解説いたします。
以上
2012年05月07日 ミャンマー・レポート 2 ~ミャンマー料理に要注意~
【コラム】
先日赴いたミャンマーのレポート第二弾をお送りいたします。
■ ミャンマー人
90%の仏教人口というデータと『ビルマの竪琴』の印象から,高い仏教熱を予想していましたが,実際はそれほどでもありませんでした。むしろ,多くのタク
シー運転手がタクシーの天井に仏?僧侶?の写真を貼り付けているタイの方が,敬虔な仏教徒が多いのではと感じました。街中を歩く僧侶の数もさほど多くあり
ませんでした。
ヤンゴンは総じて戦前ないし終戦直後の日本という印象です。紙煙草のようなものを噛んで,人が至るところに赤
い唾を吐いています。半数以上の男性がロンジーという巻きスカートを穿いている光景は,西洋化されない矜持なのか情報・物資不足なのか分かりませんが,好
感が持てます。
また,女性や子どもがタナカという白粉のような日焼け止めを頬に塗っているのが特徴的です(「ミャンマー タ
ナカ」で画像検索してヒットするその画像に驚く人も多いと思います)。タナカがあるということは,「日焼け止めクリーム」なるものが流通していないからだ
と思われます。
地理的にタイとインドの中間にあるからでしょうか,アジア系の顔ばかりではなく,インド系の顔もあります。栄 養事情のせいでしょう,身長はみな低く,170センチ以上の男性をほとんど見かけません。なお,ミャンマーの1人あたりGDPは日本の60分の1程度で す。
■ 料理
ミャンマー訪問で一番印象に残ったのが実は料理です。ミャンマー料理は正直美味しくありませんでした…。日本のガイドブックに載っているお勧め店に行き,
数品トライしましたが,嚥下に努力と気合を要する有様で,なんでも美味しく食べられることを自慢の種にしてきた私も,恥ずかしながら完食できたものはあり
ませんでした。一口食べただけで「ご馳走様」という言葉が出掛かりました。
例えば,油を使う料理(液状カレーなど)は油がとてもギトギトしています。カレーを食しているというよりは油を食
わされているような感覚に陥ります。一方,麺は逆に細くパサパサしており(コシのない春雨のよう),無味乾燥な感じがしました。ヤンゴンには日本料理も少
ないようです。日本からの駐在員が最も苦労するのは料理ではないかと思いました。
印象に残ったのは,ヤンゴン市内の「グローバル」という名のレストランに入ってチキンカレーを注文しようとした
際,メニューを見ても何を売っているのか分からないし,店員も英語を解さないし,店名にかかわらず全くグローバルではなかった点です。「カレー」すら通じ
ず,結局カレーとは全く異なるものを食す羽目になりました。
また,店員を呼ぶ際に,ミャンマー人が「シーッ」と歯の間から空気を抜いて音を出すのが印象的でした。料理の 値段は,生ビール60円,ソフトドリンク80円,料理一品200円でした。
■ 土産物がない
ミャンマーから買って帰るべきお土産が見当たりません。国際空港にも,ヤンゴン随一の観光地であるシュエダゴン・パヤーにも,ほとんどお土
産を売っていません。どこにでもよくある彫り物くらいしかありません。観光客が少ないのと,観光産業を発達させるつもりがないからだと思われます。
何もないので私は記念にアウンサンスーチーのバッジを買ってきました。ヤンゴンではスーチー女史は大人気のようで,ビルマ建国の父と謂われる父アウンサン
将軍(1915‐1947)と一緒にTシャツにプリントされていたりします。アウンサン将軍は32歳で没しましたが,ビルマ独立の前に日本の浜松に滞在
(亡命)していました。
マーケットにもアウンサン将軍の肖像画はたくさん見かけました。北朝鮮の金日成のような尊敬のされ方をしているよ
うでした。最近国会議員になったスーチー女史に人気があるのも,父アウンサン将軍の威光があってのものだと思われます。なお,アウンサンの影響か,今でも
ミャンマー国軍のパレードには日本でもお馴染みの「軍艦マーチ」が使われているそうです。ミャンマー人の多くも親日的のようでした。
■ 歴史
ミャンマーは,長い軍政のため欧米からの経済制裁を受け,世界の趨勢から取り残された感がありましたが,実は歴史的には大国だったのです。
有名なバガンの仏教遺跡の多くは13世紀までに建てられ,古い歴史を有しています。18世紀には東南アジア最強国として名
を馳せ,隣国タイのアユタヤを徹底的に破壊したのもビルマ人です。19世紀の3度の対英戦争を経てイギリスの植民地となりましたが,戦中の1943年に東
京で開かれた大東亜会議には,タイ・フィリピンと並び招聘されています。他のアジア諸国は独立国として承認すらされていなかったのです。
現テイン・セイン大統領の敷く民主化路線に伴い,最近になって経済制裁が解かれつつあることでミャンマーは世界から注目を浴びています。豊富な天然資源や安価な労働力等,日系企業にとって魅力あるミャンマーのこれからには目が離せません。
■ その他
訪問するのにビザが必要になるという面倒くささもあるのでしょう,観光客は多くありませんでした。観光客のほとんどは西洋
系で,アジア系は見かけませんでした。全体的に国中に外国人が少なく,ヤンゴン滞在3日間に街中で会った日本人は,ヤンゴン中心部の一際目立つ高層ビル・
サクラタワー20階のレストランのお客のみでした。
目抜き通りに聳え立つサクラタワーは,日系が建てたのでこの名前です。てっぺんにはHITACHIの文字。他に日系の企業
広告を見かけないので,日本の国威発揚という感じがします。他のエレベーターは,イギリス式表記に忠実で1階がGround floorで2階が1st
floorと表記されますが,日系のこのビルだけは日本式に1階が1st Floorでした。
その他開発途上にあることを感じさせる風景として,歩行者用信号が整備されていないことが印象的でした。ヤンゴン中心部で
最も横断量が多いと思われる交差点でさえ,歩行者用信号がありません。なお,旧英植民地なのにミャンマーでは車が右側通行なのは,独立後途中から変えたそ
うです。
頻繁な停電から,深刻な電力不足が懸念されます。訪問した法律事務所でも訪問中に停電が起きていました。訊けば,一日に一回は停電があるそうです。
次回第三回は,ミャンマーの法律事情をお届けします。
以上
2012年05月01日 ミャンマー・レポート 1
【コラム】
中山達樹です。3月末から4月初旬にかけて,ミャンマーのヤンゴンに法令調査等のため出張して参りましたので,数回に分けてご報告します。
■ 概要
ミャンマーの面積は日本の約2倍で,人口は約6000万人。政治的理由で長らく欧米諸国から経済制裁を受けていましたが,昨秋のクリントン米国務長官の訪問後,マーケットしての成長性・生産拠点としての可能性に注目が集まっています。
2006年からネピドーが首都になりましたが,長くヤンゴン(1989年までラングーン)が首都でした。ヤンゴンの人口は約400万人。狭いです。10分車で走れば,すぐ郊外に出ます。その狭さはシドニーに似ます。旧英植民地のせいでしょうか,道路はRoundabout(環状交差点)などがあり,案外整然としています。
ヤンゴンの見るべき仏教遺産は…はっきり行ってそれほど時間は掛かりません。ですからヤンゴン観光は一日で足りると思われます。ミャンマーに行く余裕が二日あったら,一日は世界三大仏教遺跡の1つ,バガン(ヤンゴンから飛行機で約1時間)に行くことをお勧めします。
そのヤンゴン,飛行機が空港に着陸した途端,50年近くタイムスリップしてベトナム戦争に来たプラトーンの一員になった気がします。野生の血が騒ぐとでもいった感じでしょうか。それは空港の周りがジャングルであり,空港も滑走路以外舗装されてないという原始的な姿を見せているからです。アフリカのブルキナファソという小国に行ったことがありますが,その空港と比べても遜色のない規模でした。ただ,空港内は綺麗に整備されており,規模は小さいですが,ジャカルタの国際空港より綺麗でした。
ヤンゴンの車,見た感じでは7割以上が日本車でしょうか。古過ぎて国籍不明の車も多いです。うち半数以上は,1960年?70年頃?製造と思われるようなトヨタ車が多いです。タクシーもそうです。後部座席のシートがボロボロで,女性が生活するのは大変だろうと思わされました。タクシーはみな,今まで乗ったことのないオンボロ車でした。また,街頭テレビに群がる人々を見て,昭和30年代の日本の風景もこうだったのだろうと思いました。
ヤンゴンのどこを探しても,マクドナルドもスターバックスもコンビニも一軒もありませんでした。東南アジアでは街中いたるところに見かけるマッサージ屋も一つも見かけません。空港にもありません。長らく鎖国同様の状態にあったため,サービス産業が未発達のようです。ホテルのスタッフと接しても,サービス精神旺盛な「微笑みの国」隣国タイに比べると,ミャンマー人のサービス精神・レベルは見劣りします。
都心ばかりではなく,あえて郊外を見ようと思い,タクシーを40分くらい走らせて日本人墓地に行きました。先の大戦時に,19万人もの日本兵が亡くなったようです。東日本大震災の10倍です。墓地自体の規模はたいしたことありませんでしたが,その墓地の周りで暮らすミャンマー人が,いわゆる「高床式住居」に住んでおり,上半身裸に裸足で暮らしているのが印象的でした。私が今まで見た中で,最も原始的・牧歌的な暮らしをしている人々でした。
日本人墓地から帰りのタクシーを拾おうと思い英語で話しかけましたが,このような人々は英語を全く解しません。「ミャンマーは旧英国植民地だから英語がある程度通じる」と訊いていましたが,総じて,ヤンゴンの市井の人に英語はほとんど通じませんでした。ヤンゴンでも指折りのトレイダーズホテルの従業員の英語のレベルも,高くなかったです。もっとも,弁護士など知的職業に就く年配の人では,英語がとても上手な人がいます。訊けば,幼稚園から英語を学んでいたからだそうです。
帰国時,日曜日夕方であり利用者が多いかと思いきや,国際空港は閑散としていました。イミグレのオフィサーが机で昼寝していたのが印象的です。
「インドに行くと人生観が変わる」と巷間謂われますが,私は今のミャンマーに来た方がはるかに人生観にインパクトを与えると思います。この国の,原始的な生活や今後の発展を予感させる活気を見ると,元気が与えられます。
■ 気候
気温は35℃以上で,バンコクと同程度ですが,ヤンゴンの方が湿度が高いです。一週間前にバンコクに行った際は,いわゆるビジネスマンはみなネクタイを締めていましたが,ヤンゴンではネクタイを締めている人は一人も見かけませんでした。私も弁護士事務所等を訪問するべくネクタイを締めて臨もうと思いましたが,すぐ外しました。
冷房が付いているタクシーは少なく,移動するだけで汗まみれになります。湿度が高いせいか,ヤンゴンで靴を履いているのは外国人観光者だけです。ローカルはみんなサンダルです。たまに素足の僧侶を見かけます。
こんなに蒸し暑いヤンゴンですが,短パンの男性は見かけません。これはアメリカナイズされていないからだと思います。シンガポールでも感じましたが,インド系の人々も短パンを好みません。
次回は驚愕のミャンマー料理などについてご報告します。
以 上
2012年04月17日 インド・レポート ~IPBA総会に出席~
【コラム】
IPBA(環太平洋法曹協会)の年次総会に出席するため,2月末から3月初旬にかけてインドのデリーへ出張してきましたのでご報告します。
■ IPBAとは
IPBAとはInter-Pacific Bar Associationの略で,20年余りの歴史がある世界の弁護士団体です。環太平洋地域のビジネスに関心を持つ弁護士が主に参加し,世界中で1,700人程度の会員を有しており,毎年環太平洋地域で行われる年次総会には1,000人程度が出席し,種々の情報交換等を行います。
その創立に当事務所の三宅能生弁護士が大きく関与したことから,私も当事務所入所以来そのメンバーになり,これまでロサンゼルス,マニラ,シンガポール,京都で行われた年次総会に出席してきました。今年のインドの年次総会は5度目の出席となります。5度の出席となると知り合いや友人も増え,年次総会での交流が楽しいものになってきます。
今回は,インドに対する日系企業の投資熱の高さを反映してか,約900人弱の総参加者のうち,日本人だけで150人程度もいました。来年はソウル,再来年はバンクーバーで年次総会が行われます。
■ インド
昨年1月に京都大会のプロモーションでデリーを訪れて以来,私にとってインドは2回目の訪問です。日本人のインドに対する印象は,観光地域に関する印象に偏っていることが多いようですが,インドの商業地域は他のアジア地域と大差がないくらい発展しています。総じて,インドの都市部は他のアジア地域と大差ないと私は感じています。
今回も,デリーから車で5時間くらいをかけてタージマハルへ行きましたが,その途上で見かける風景も,特に衝撃的なものはありませんでした。道は舗装されていますし,往来に困ることもありませんでした。巷間「インドに行くと人生観が変わる」と言いますが,まだ私はそのようには思いません。いずれおってご報告しますが,ミャンマーへ行った方がその「未開さ」に衝撃を受けると思います。
実際,一人あたりGDPで見ると,インドはまだ他のアジア諸国に遅れを取っていますが(ベトナムと同程度),インドのホワイトワーカーの給料は他のアジア諸国の給料と大差ありません。もっとも,自動車が決められた車線を走らず,絶えずクラクションを鳴らしながら賑やかに走るのは,「さすがインドだ」という感じがします。
また,デリーの中心部で,一度だけ「子どもにまとわりついてお金をせびられる」という経験をしました。これはなかなか他国ではできない経験です。なお,「ああいう子どもには決してお金をあげないように(後ろでお金を吸い上げる大人を利するだけだから)」とシンガポール国立大学のインド人の教授に教わりました。
全インドにはまだ日本人は4,000人程度しか滞在しておらず,タイの10分の1程度です。日本からの進出企業はまだ自動車産業などが中心ですが,これからは多業種になってくると予想されます。
■ インドの法律
昨年に『アジア労働法の実務Q&A』を刊行して以来,アジア各国の労働法の動向は注視しています。今回のインドでもインド人弁護士にインド労働法の特徴等を聴取したところ,案の定,「インドでは労働組合が強い」という回答が帰ってきました。その理由としては,以下の2つが考えられます。
まず,「超」格差社会。インドでは日本とは比べ物にならないくらい,上層労働者と下層労働者の格差が離れています。例えば,法律事務所でいわば「お茶汲み」をする男性がいましたが,いかにもみすぼらしいというか,格差を感じる格好・風貌をしていました。
2つ目は,余り知られていませんが,インドは1990年まで社会主義的経済体制にありました。その残滓から,社会主義の影響が色濃く残り,ために労働組合が強いそうです。
このように労働組合が強いインドですが,ストライキも多く,スズキ自動車(インドではマルチスズキ)で昨年大規模なストがあって工場の操業が停止し,その影響でスズキのシェアが約10%も落ちました。実際,1年ぶりにインドの地を踏み,「スズキの車が減ったな」と思いましたが,これはストの影響だったようです。
■ インドの法律事務所
日本のように,一等地に構えた瀟洒なオフィスビルにオフィスがある法律事務所は多くありません。デリーの高層ビルも日本のように何十階という高いものはありません。
今回,中規模程度のインドの法律事務所を訪問しましたが,住宅地の一角にあるそのオフィスも,お世辞にも快適な職場環境とは見えませんでした。もっとも,豪華なオフィスを構えれば設備費・維持費等はクライアントに転化することになるわけですから,どちらがclient friendlyなのかという気はします。
以 上
2012年04月17日 タイ・レポート ~国際交流委員会 活動報告~
【コラム】
第一東京弁護士会の国際交流委員会の研修で,タイの法曹事情等視察のため3月19日と20日にタイのバンコクへ出張してきましたのでご報告します。
■ 弁護士会訪問
弁護士会の施設は,バブリーな東京の弁護士会館とは異なり,その辺にあるような4階建てくらいの建物です。タイの一人当たりGDPは日本の約8分の1だから推して知るべしですが。列席したタイ弁護士会のほとんどの人は通訳なしで英語を解します。翻って日本の弁護士会の上層部,通訳なしで英語を解する人はどれくらいいるのでしょうか。
外は35℃を超える熱さだというのに,室内は冷房が直撃して寒いのと,出されたコーヒーがデフォルトで甘い(砂糖もミルクもたっぷり入っている)ことから,ああ東南アジアに来たと実感します。頂いた名刺に Lawyers Council of Thailand “Under the Royal Patronage”の文字。名刺も一般の名詞より紙質・印刷ともに上質。タイは肩書社会と謂われますが,「王室公認」たることを示すこの名刺も神通力のような効力を有するのでしょうか?
なお,会議室の正面左手にはブミポン国王と王妃の若き日の大きな額入りの写真。弁護士会会議室のみならず,タイでは至るところに国王の肖像を見かけます。戦前戦中の日本もこうして天皇の御真影を掲げていたのでしょう。
タイ弁護士会は1985年に設立され,日弁連のような連合体ではなく,全国統一組織です。独立性を謳ってはいますが,政府からの資金援助を受けています。タイの弁護士数は6万人弱,人口が日本の約半数であるのに弁護士が2倍近くいるということは,人口1人あたりの弁護士数はタイの方が約4倍も多いことになります。
弁護士会の活動自体は特に日本との顕著な違いはないようです。弁護士資格を取得するのに4年制大学の法学部を出る必要があるというのは,イギリス的。大学院へ行く人は単に箔を付けるためらしいです。この点は日本やアメリカのロースクール(大学院レベル)と異なります。
タイ弁護士の女性比率を訊くと,特に若手弁護士では女性の比率が非常に高く,大学の法学部にも女性が多いらしいです。男は何をやっているの?と訊いたところ,遊んだり歌手を目指したりしているという冗談ともつかぬような返答が返ってきました。タイのみならず東南アジアでは女性の弁護士比率が日本に比べ顕著に高いです。日本もロースクール制度になって女性の比率は増えるのでしょう。
IPBA(環太平洋法曹協会)の会長も務めたこともあるKrairit氏と同席しましたが,聖書に由来するユーモアを披瀝するなど,さすがと思わされました。どの国にも通用するユニバーサルな話題は,このような席に備えていくつかネタとして持っておきたいものです。
■ 裁判所見学
バンコク最大の民事裁判所見学。建物はお世辞にも綺麗とはいえません。日本の地方の地裁の支部程度という感じでしょうか。所長らからタイの裁判についてレクチャーを受けました。労働裁判と消費者裁判では,市民が口頭かつ無料で提訴できるという制度は,ある意味進んでいます。しかし提訴にあたり弁護士のチェックを受けないのですから,濫訴の危険はあるのでしょう。そうなれば裁判所の負担は増えます。無料・口頭で提訴ができるというのは一見「進んだ」システムでしょうが,裁判全体の効率という観点から見ると,デメリットもあるでしょう。
法廷内の正面(裁判長席の後ろ)にもブミポン国王の写真が。シンガポールの法廷正面にも国家を象徴するエンブレムがありました。これらに比較すると日本の法廷には「日本」を感じさせるものは何もないため,いかにも殺風景です。
日本と同様,裁判官は黒い法服を着て法廷に立ち,弁護士もダークスーツと上品なタイで出頭することが要請されています。法廷に立つ弁護士にドレスコードがあるのはシンガポールと同様です。そのような要請がない日本の裁判所がむしろ例外なのでしょうか?
■ 日本大使館・JETRO訪問
洪水の被害が出たのは,例年1つか2つしか来ない台風が5つも直撃し,また,バンコクから北部アユタヤまでの80kmで高低差がわずか9メートルしかないという平板な地形のせいです。なお,今年4月からタイの最低賃金は上昇しており,これがタイ日系企業に与える影響がどれくらい大きいのかも個人的には懸念していました。
しかし,公使やJETRO職員に訊くところによれば,洪水や最低賃金上昇にもかかわらず,タイから撤退する日系企業は非常に少なく,1割にも満たないそうです。洪水被害のないタイ国内の別地域に工場を移転する企業が多いようです。2012年の経済成長も5%以上と予測されています。
特に自動車産業では,タイには他の国を凌駕するサプライチェーンが発達しているため,撤退したくともできないというのが実情のようです。今年1,2月には工場建て直しのために日本からバンコクに日本人が殺到し,日本人が集まる店は軒並み賑わったそうです。
日系企業のタイ進出は堅調に伸びており,在タイ日本人(現在5万人程度)は10年前の2倍を超えています。東西・南北回廊を嚆矢とするメコン地域の開発が進めば,タイの地政学的な優位性もより際立つでしょうから,今後もタイ進出の重要性は変わらないと思われます。
以 上