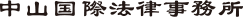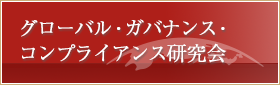2013年12月30日 シンガポール・レポート
【コラム】
シンガポール・レポート
2013年11月末,2011年6月の帰国から約2年半ぶりにシンガポールに行って参りましたので,ご報告します。
1 China-Japan Young Leaders Forum(日中若手リーダー会議)
(1) フォーラム概要
渡星(シンガポール訪問)の目的は,China-Japan Young Leaders Forumへの出席です。シンガポールのリー・クアンユー公共政策大学院Huang Jing (黄靖)教授と,『失敗の本質』で著名な野中郁次郎富士通総研理事長の発案により,同大学院Centre on Asia and Globalisation と㈱富士通総研経済研究所の共催で,今年初の試みとして行われました。
将来的な日中友好を目的として,各界(政財界・学界・ジャーナリズム・民間)で活躍する日中の主に30代の若手が,様々なテーマで議論するというものです。今回は日中から8名ずつ,経産官僚,教授,テレビ局員,企業家,コンサルタント,NPO法人などが集まり,弁護士としては私のみが出席しました。
討論のテーマは,①日中関係(総論),②NPO法人やメディアの役割,③グローバリゼーションと日中相互の経済依存を柱として多岐にわたり,朝から晩まで徹底的に英語での議論を楽しみました。
日中関係は,尖閣や靖国問題などで非常にセンシティブになっています。しかしながら,腹を割って話し合わないことには真の理解も友情も生まれないとの信念のもと,繊細な問題についても大いに討論することができ,大きな収穫がありました。
(2) 相互理解の重要性/中国から学び得ること
具体的には,先の大戦では日本軍はアジア各地で同様の行為を(いい行為も悪い行為も)したにもかかわらず,東南アジアの人々が極めて親日的であるのに中国人がなぜ反日であるのかについては,中国政府による国民への過度の反日教育の他に,中国人が自国の歴史に強い思い入れを持っている点も挙げられることが分かりました。
また,靖国問題については,死ねば悪人ではなくなる(死者に鞭打たない)という日本の死生観に対して,中国では(靖国で悪人を祀っていると評価した上で)悪人は死んでも未来永劫悪人であるなど,文化・価値観の違いも大きいように思います(これはあまり報道されていないようです)。
さらに,共産党という一党独裁,表現の自由ないし検閲という中国の特徴というか課題についても議論しました。現代中国で,日本の元ポルノ女優(蒼井そら)が有名であること,若者には無気力・倦怠感が蔓延していること(そういう若者をdiao si=吊丝というそうです)なども勉強になりました。
我々が中国から学ぶべきというか参考になると思ったのは,中国における政治指導者輩出システム(共産党員として,組織で出世するために数十年のスパンで篩に掛けられる)が,日本の現在の民主政ないしはポピュリズム(テレビで有名になればすぐ政治家・首長になれる)よりも慎重かつ賢明なのでは,という問題提起です(なお,シンガポールでも,政治家になるためには,学歴・経歴・資産・人格その他を総合考慮した厳しいスクリーニングに合格する必要があります。)。自国ないしその制度を他国の視点から客観的に見つめ直すことの重要性を改めて思いました。
(3) 日中の「壁」とは?
個人的には,激しい討論の後の打ち上げで,開放感と友情から,中国側代表と熱くダンスに興じたひとときが,最もよい思い出になりました。ネットで悪口を言い合うのではなく,顔を合わせてまずは話し合うこと。日中友好はこのような地道な努力から始まると信じています。
日中には様々な「壁」があるように思われていますが,その壁を作っているのは実は我々の心というか態度(心理的嫌悪感)にあるのかも知れません。今後も,このフォーラムを通じて日中友好に貢献できればと思っています。
2 シンガポール事情
(1) シンガポール・バブル
シンガポールでは,国中の至るところに高層ビルの建築が進んでいます。シンガポール・バブルとも言われていますが,その勢いは衰えを見せていません。家賃も,私がいた2年半前の1.5倍になっています。
その他,外国人の受入れに限定的になっており,日本人でもある程度の給料が得られるのでなければ,シンガポール入国のビザが発給されなくなっています。
私がシンガポールを去ってから2年半のうちに新しくできたシンガポールの見せ物としては,シンガポール動物園に新設されたリバー・サファリと,湾岸地域にできた植物園ガーデンズ・バイ・ザ・ベイがあります。後者は1時間程度散策しましたが,有名ホテルのマリーナ・ベイ・サンズやその他の摩天楼を背景に広がる植物園の眺めは,格別なものがありました。
(2) 建国以来の暴動
2013年12月8日午後9時過ぎ,インド人街交差点でバスが歩行者をはねる交通事故が発生し,これに端を発して400人規模の大規模な暴動事件が発生しました。この暴動によりバス,警察車両,救急車が破壊,転覆,放火され,南アジア出身者27人が逮捕されました。「シンガポールでは,こうした暴動の発生は過去40年以上発生しておらず,建国以来,初めてのもの」(日本大使館)だそうです。
2年前の総選挙で与党が得票率を落とし,建国の父リー・クアンユーが政治家を引退してから,数十年ぶりにストライキも発生したりして,国としての求心力が衰えつつあるように思われます。シンガポールが成熟した先進国入りしたことの副産物と思われますが,この課題にシンガポールがどのように対処するのか,着目したいところです。
3 シンガポールの日本人弁護士業界
私がシンガポールに留学した2009年は,当地にいる日本人弁護士は私を含めてわずか3名でした。しかし現在は,日本のいわゆる大手法律事務所がシンガポールにオフィスを開いていることもあり,シンガポールにいる日本人弁護士はおそらく30名を超えているのではと思われます。ロースクール導入後に日本の若手弁護士の勤務形態が多様化していることも一つの理由ですが,それだけ,東南アジア及びシンガポールに進出する日系企業が増えていることの現れだと思います。
アベノミクス3本目の矢で,成長戦略の一環として,今後5年間で1万社の日系企業を海外進出させることが閣議決定されました。国際業務を取り扱う我々としても,依頼者の目線に立ったよりよいサービスを提供してゆかねばという自覚を新たにしています。
以上
2013年12月30日 東南アジア労務の特徴
【コラム】
東南アジア労務の特徴
チャイナリスクが顕在化した近年,多くの日系企業が東南アジアに進出しています。進出後に日系企業が必ず直面するのが,労務問題です。
日本とは異なる文化・民族・宗教等が絡むため,現地の労務問題は扱いにくいと言われています。そこで,東南アジアの労務問題の注意点をいくつか挙げてみます(「東南アジア」にも様々ありますから,安易に一般化することは控えねばなりませんが,それでも労務の観点からはいくつかの共通項を挙げることができます)。
まずは,以下の諸点において,東南アジアの日本との違いを認識することが大事です。
1 宗教
(1) 仏教国
タイやミャンマーは仏教国であるため,日本人と価値観が共通する点も多く,考え方が理解しやすいと言われています。
(2) イスラム教
一方,マレーシアとインドネシアはイスラム教徒が多いため,イスラム教徒と接することが少ない日本人は特別な配慮が必要です。例えば,イスラム教徒のラマダン(断食)の時期においては,腹を空かせた労働者による生産性・業務効率が落ちたりします。
なお,マレーシアの方が厳格・敬虔なイスラム教徒が多く,インドネシアのイスラム教は穏健と言われ,インドネシアには酒や煙草にも寛容な人が多くいます。
(3) カトリック
フィリピンはカトリック教徒が多いです。クリスマスの時期に,貧しい人も家族になんとかしてクリスマスプレゼントを買おうとし,資金捻出のために強盗を働くという「クリスマス強盗」があるので治安が悪化したりします。
2 気候的要因 -暑いと人間は働かない?-
(1) 気温と労働生産性の相関関係
最近でこそ日本は夏の35度を超える暑さに四苦八苦していますが,東南アジアは年中「酷暑」です。タイでは40度近くにまで気温が上がることがよくあります。つまり,毎日が真夏であり,毎日が酷暑です。海に近いシンガポールなどでは湿度も高く,文字どおり「うだる」ような暑さです。
こういう地域に住む人々は,有史以来,「暑い日中に汗水垂らして働く」という概念がそもそもありません。日本の九州や沖縄でも,夏の正午~午後2時に外で働く人をほとんどみかけませんが,これが365日のデフォルト・スタンダードなのです。
近代以降,クーラーの発達でシンガポールが発展する以前,赤道付近にいわゆる有力国はありません。ある程度以上暑いと,やはり人間の勤労意欲は減退するのでしょうか。恥ずかしながら私もシンガポール滞在時,自宅で夜に冷房をつけないと仕事・勉強の能率は上がりませんでした。このような気候からくる気質からか,東南アジアでは,日本人が求めるような勤勉さが過大要求になることがあります。
(2) 転職率との相関関係
また,東南アジアには,日本と異なり失業を恐れない価値観が広がっており,これが転職(ジョブ・ホッピング)の頻繁さと関係していると言われています。これは,辛抱強く農耕を営まなくても,豊富な果実が採れるために,有史以来,働かなくてもなんとか生き延びることができた南国特有の価値観でしょうか。
いずれにせよ,ジョブ・ホッピングが頻繁な東南アジアでは,せっかく労働者のスキルを上昇させてもその労働者が簡単に辞職することがままあります。そのため,労働者を継続雇用するために,如何に魅力的な職場環境を維持するかという点に最大限気を配らないといけません。
3 家族至上主義
(1) イスラム教徒のお祈りの対象
特にマレー系民族やイスラム教徒において顕著ですが,日本人と異なり,仕事・労働にはいわば二の次三の次の優先順位しかなく,人生において最も価値があるものは家族と考えている人が多いです。例えば,イスラム教徒が行う一日に5回のお祈りにおいては,キャリアアップや自己実現などではなく,多くは家族の安寧を祈りの対象としているようです。
むしろ,日本人のように「愛社精神」や会社への強い帰属意識を持っていることが特別であるという自覚が必要です。当然,終身雇用的な価値観も基本的になく,ジョブ・ホッピング(少しでも給料の高い会社へ転々と転職すること)が一般です。
そのため,家族至上主義とでもいうべきでしょうか,「奥さんがちょっと体調を崩して…」という日本ではあまり見られない軽微な理由で仕事を休む人がいたりします。業務上の失態の言い訳で何かと家族を持ち出したり,いい年をした大人が,親の意見で就職・転職・辞職を決めることがあったりするのも,日本にはない傾向といえます。
一方,家族への愛着を逆手にとって,家族旅行をインセンティブにする(出来のいい社員に家族旅行をプレゼントする)と喜ばれたりします。
(2) 家業との密接な関係
また,多くの日本人のように一つの職場で専念するのではなく,家業や個人事業との兼業をしている労働者が多いのもアジアでの特徴です(そして,これがリベートやキックバックの温床になったりします)。
4 途上国は「日本の昭和」
(1) 農業中心
シンガポールなど一部の商業・工業国を除いて,アジアではまだ農業従事者が大半を占めます。つまり,歴史的に,「企業(会社)」で働く経験がなかった人々がたくさんいます。そのため,組織全体のことを考えて規律のある行動をとることが不得手であることがあります。
具体的には,退職時に業務の引継ぎをしないとか,「ホウレンソウ」ができないとか,守秘義務を守れない,言われたこと(自分の業務)しかできない…などの問題点があります。その他に,ミャンマーではスーツを着たことはおろか見たこともない人がスーツを作っていたり,カンボジアでは水洗トイレを見たことがない人が便器で顔を洗ったりします。このような人々と根気強く付き合う覚悟が必要ですし,だからといって「上から目線」で接するのではなく,現地でビジネスをさせていただくという謙虚な姿勢も大事です。
(2) 時間にルーズ
日本人は世界的に見ても時間を厳守すると思われていますが,アジアではそもそも,正確な時刻を刻む時計を持っていない人が多いです(スマートフォンの普及により改善していると思われますが)。ですから,そもそも時間厳守を日本並みに要求することは難しいと観念することも必要かもしれません。
(3) 強力コネ社会
また,特に途上国であればあるほど,人的なコネ・人脈がモノをいう社会です。家族や親戚縁者への横流しやキックバックが日常茶飯事で,当地の人々はそこに罪悪感を感じておらず,当然の所為としていることが多いです。
これらの横流し等に対して日本的な厳格なコンプライアンスを完全に要求すると,現地スタッフの強い感情的な反発を食らったり,それが原因でビジネスがにっちもさっちもいかなくなったりすることもあるので,ある程度柔軟な「アジア的」解決を選択肢に入れることも必要かもしれません。
(4) 頻発するストライキ -インド,インドネシア,ベトナム-
さらに,大卒率が低い国ではストライキが多いという傾向があります。インド,インドネシア及びベトナムです。これは,製造業のブルーカラー労働者の大半を占める小中高卒の労働者が,労組幹部に安易かつ軽率に扇動・洗脳されやすいことから説明できると思います。
(5) 低い識字率
なお,識字率が低いと簡単なマニュアルも理解できないために,労働生産性がガクンと低下します。ASEAN主要国は高い識字率を維持していますが,カンボジアやバングラデシュは識字率が低いため(カンボジア7割,バングラデシュ5割程度),注意が必要です。
以上要するに,「労働コスト安」であるから東南アジアに進出している企業が多いと思われますが,労働コスト安は,必然的に,「教育・訓練コスト高」を招くことを覚悟しなければならないと思います。
5 おカネに対する執着
日本では,職場を選択する際には,自分に合った職種か,希望する仕事ができるか,安定性・将来性のある企業か,という点が多く優先されます。しかし,東南アジアでは,そのような希望職種や業務内容等よりも,高月給というだけの理由で就職先を選ぶことも多いです。
ですから,現地労働者が自己の勤務先・仕事に対して愛着・親近感・誇りを持っているとはあまり期待できません。そのため,アジア諸国では,ジョブ・ホッピングすなわち労働者が少しでも高い収入を求めて次から次へと転職することも多いです。
また,現地企業や中国や韓国系の企業では,コンプライアンスが不十分で最低賃金を支払わない企業があったりしますが,最低賃金を守っているだけで日系企業の評判が良かったりします。現地労働者が日系会社に勤めている理由が,単に「最低賃金がちゃんともらえるから」である場合もあります。
このような価値観の相違があるため,経営側としては,相当程度の給料・手当を支給するだけではなく,職場環境を改善するなどしていかに従業員を定着させ,いかに会社への帰属意識を高めてもらうかが重要な課題となります。その具体的な対策については後述します。
6 オリエンタル・スマイル
インドとミャンマーを隔てるアラカン山脈以東の東南アジアでは,世界の他の地域と異なる顕著な特徴があります。それは,人々が多く笑うこと,より具体的には,悪いことをしたときや気まずいときに,笑ってごまかそうとすることです。ちなみにこれは日本人にも共通すると思います。私はこれを「オリエンタル・スマイル」と呼んでいます。具体的には,タクシー運転手がおつりを渡さないときの表情が典型的です。東南アジアでは,多くの運転手が(おそらく本当はおつりがあるのに)「Sorry I have no change, boss」と言っておつりを渡すのを拒みますが,経験がある方は,その際の運転手の表情を思い出してください。おそらくニヤニヤと笑っているはずです。そして東南アジア以外のタクシーの運転手は,そのような,媚びた面従腹背的・阿諛追従的な笑いをしないことが多いと思います。
文化人類学的に,長きにわたり植民地支配を受けたことの影響で,面従腹背的な行動様式がDNAに刷り込まれていると言う人もいますが,いずれにせよ,現地労働者の「笑顔」に騙されないことが大事です。日本人と同様,多くの東南アジアの人は,面と向かってNoと言うことが苦手で,とりあえずその場を繕うため(もしくは保身のため?)に,Yesと言ってしまうことが多いようです。ですから,現地労働者の弥縫策的なYesを真に受けないこと,性悪説的な立場に立つことも時には必要です。
なお,Noと言わないという点ではインド人も同様で,インド人が「OK, sir.」と言ったとしても,それを「分かりました」と真に受けるのではなく,「聞こえました」くらいに解釈するのがいい,と思うこともあります。
とはいえ,どういうわけか,東南アジアには羞恥心が強く,秘めたプライドが高い人が多いようです。そのため,労働者を人前で叱責することは多くの国でご法度と思われています。
7 配置転換・異動に対する価値観
日本の特に大企業で若年労働者に対してよく行われる配置転換・異動(例えば,営業スタッフを総務に,など)は,たしかに癒着防止や多様な職種を経験させるなどのメリットもありますが,海外ではむしろその労働者のキャリアを切断するというデメリットの方に気をつけた方がいいと思います。つまり,配置転換(異動命令)は,その労働者のこれまでのキャリア形成を無視するものなので,これを「懲罰」と感じる現地スタッフが多いです。
しかも,多くのコモンロー諸国(マレーシア,ミャンマー,インド,フィリピン)では,Constructive
Dismissal(みなし解雇)といって,労働者の意に沿わない異動・配置転換命令等に対して,会社ではなく,労働者側が,解雇手当の支払を求めて,「それはもはや解雇に等しい」と主張することがあります。このみなし解雇は日本にはない概念なので,特に注意する必要があります。なお,解雇手当も,日本とは異なり,法定されており(だいたい,1年の勤務に対して1か月分の給与相当額です),懲戒解雇以外の解雇の場合には,解雇手当の支払は覚悟しないといけません。
8 裁判はあてにならない
(1) 法曹のレベルと不公平な裁判
シンガポールやマレーシア以外のアジア諸国では,まだ裁判官や弁護士のレベルは低いと考えた方がいいかもしれません。ベトナムでは,裁判官に法曹資格はありません(共産党員が裁判官になっています)。そのため,日本ではおよそ提訴しないような事件でも,アジアでは裁判を提起されることがありますし,「大岡裁き」のような大雑把な判決が下ることもあります。
裁判官の給与が低いインドネシアでは,賄賂が裁判官の重要な生計の足しになっているといわれ,裁判結果が汚職に左右されるといわれています。インドネシア以外でも,いわゆる「ホーム・アウェイ」の判断が行われ,日系企業ではなく現地労働者を保護する判決が出るおそれがあります。要するに,裁判で正義が通ることを期待できないと観念した方がいいことが多いです。
しかも,インドにおいて特に顕著だと思いますが,提訴に抵抗がなく,日本人と異なり,すぐに裁判を起こす傾向があります。
(2) 現地語での裁判
また,どこの国でも,裁判は現地語(タイならタイ語,ベトナムならベトナム語)で行われます。そのため,すべての裁判書類は裁判で使用するためには現地語に翻訳しなければならず,証人尋問では通訳を使用する手間とコストがかかります。
(3) 東南アジア的解決
このように考えると,紛争リスク・裁判リスクは,日本に比べると格段に高いといえます。そのため,裁判するくらいなら,ある程度高い授業料を払っても裁判以外での解決を志向するという「東南アジア的」解決が選択されることがあります。日系企業では,解雇した労働者に対し,法定の解雇手当を上回る+αの金銭(例えば,一か月分の給料)を支給することがあったりしますが,これはその「東南アジア的」解決の一例といえます。
以上が東南アジア労務の特徴です。解決策については別項<東南アジアの労務対策>でご紹介いたします。
2013年12月30日 東南アジアの労務対策
【コラム】
東南アジアの労務対策
東南アジア労務の特徴で述べたような日本との違いを念頭に,東南アジアではどのような労務対策をとるべきでしょうか。いくつかの解決策をご紹介いたします。
1 現地従業員との綿密なコミュニケーション
(1) 現地語取得の重要性
何と言っても,日頃から現地スタッフと丁寧かつ親密な意思疎通を図っておくことに尽きます。その意味では,日本における日本人との労務問題と同様といえます。ストライキが多発するインド・インドネシア・ベトナムにおいても,スト対策として「これ」といった特効薬があるわけではありません。
東南アジアでネックなのは,言語です。英語ができる人が多いシンガポール,マレーシア,フィリピンはともかく,それ以外の国では,現地スタッフは,中間管理職はともかく,英語はほとんど話せません(ミャンマーでも,管理職以外とは英語は通じません)。そのため,駐在する日本人が現地語を話せない限り,末端労働者との間まで意思疎通をすることが難しかったりします。実際,英語のできる中間管理職的現地スタッフとのみ意思疎通を図り,それ以外の現地スタッフとは会話もしない(できない)という日本人が多いのではないでしょうか。
しかしながら,それではどうしても末端労働者との意識の差を埋めることは難しく,彼ら彼女らの不平不満を上手く汲み取ることも難しいです。例えば,現地スタッフが不満に思うのは単に給料の額だけではなく,社食の味からトイレの清潔さまで,文字どおり多岐にわたります。
(2) 家族主義的考えまた,日本人とはプライバシーの感覚が異なり,会社を「家族的」な組織として捉える現地スタッフも多く,例えば,労働者の配偶者の誕生日にまで配慮したりすると,非常に好感を持たれることがあったりします(これは日本ではまずあり得ないと思います)。そのため,可能な限り,現地語を取得して,なるべく多く現地スタッフと会話する機会を持つようにすることが有用です。
(3) 由らしむべし,知らしむべし!
日本でもそうですが,日系企業の経営理念を,末端労働者まで浸透させる努力が大事です。上述のような「言語の壁」があるため,日本親会社・現地子会社の経営理念を,英語の話せる中間管理職的現地スタッフに伝えるだけで,末端労働者まで伝えようと努力しているケースはそれほど多くないかもしれません。
しかしながら,どこの国でも,経営理念や企業方針を浸透させることは重要であるはずです。まずはきちんと「知る」ことが理解と親近感の始まりです。現地スタッフが経営理念等をよく知れば知るほど,経営陣に敵対的になることも少なくなり,ストライキも減ると予想されます。
論語に「由らしむべし,知らしむべからず」という言葉があり,為政者が市井の人にまで事細かく政治理念等を知らせる必要はないという乱暴な前時代的意見があります。しかしながら,現地企業の経営の円滑化のためには,現地スタッフの末端まで,会社理念や経営方針を徹底的に「知らせる」努力が必要だと思われます。
2 労務を人事で予防
(1) 駐在員の適性
ではどのような日本人人材を現地へ駐在させるべきかについて管見を述べます。
文化や言語の違いから,基本的には現地スタッフは(失礼ですが)「十を聞いて一を知る」人々が多くを占めると覚悟した方がいいかもしれません。
そのような現地スタッフとも根気強くコミュニケーションが取れ,人任せにせず,責任感があり,バイタリティのある人材が望ましいといえます。
(2) 英語のレベル
語学については,堪能であることに越したことはありませんが,現地でさえブロークンな英語がまかり通っていますから,あまりハードルは高く考えない方がいいかもしれません。上述のとおり,英語に加えて現地語の取得も望ましいです。特にインドネシア語はかなり簡単といわれています。
何が正解ということはありませんが,例えば,場合によっては,日本人同士でも,日本語ではなく英語で話すことにより,現地スタッフへ配慮するなどの工夫も必要かもしれません。
3 具体的対策
上記の他,労務対策・ストライキ対策として有用と思われるものを以下に列挙します。
(1) 予防策
・ ご褒美としての日本研修(東南アジアは超が付く親日的国家群で,日本旅行は現地スタッフから見ると「夢のまた夢」なので,非常に魅力的なインセンティブになる)
・ 無記名投票箱の設置
これにより日常の不平不満の吸い上げ
・ 他社に負けない賃金レベルの維持。
そのための情報収集も大事。
・ 賃金以外の手当も当然充実させる必要あり
・ 食事の味や質の改善
・ 食堂やトイレの清潔さの維持
・ 制服の見栄えの良さを確保
・ 下駄箱やロッカー等の設備の充実度チェック
・ 会社の一体感・連帯感を醸成するイベント・福利厚生
例:運動会,懇親会,誕生会,社員旅行など
・ 昇給,褒賞などの昇給基準の透明化
(2) ストの善後策
・ ストに備えて在庫を確保しておく
・ 取引先にも,複数社から仕入れるよう事前に依頼して予防線を張っておく
・ 違法行為には毅然とした措置を
・ 警察・領事館・政府当局・上部組合との連携・介入要請
2013年10月12日 インドネシア当事者との契約における使用言語について
【コラム】
インドネシア当事者との契約における使用言語について
アジアでは,日本と異なり,法律が存在しても施行細則がないために法律が空文化していたり,法律の定めがしかるべく運用されていなかったりすることがあります。以下のインドネシアの例が好例です。
インドネシアでは,インドネシア当事者との契約にはインドネシア語を用いなければいけないという法律があります(Law No. 24 of 2009の31条)。上記「契約」の種類等に何らの限定がないため,理論的には,いやしくも契約の相手方がインドネシア人またはインドネシア法人であれば,すべてインドネシア語で契約しなければいけないという建前になっています。なお,施行細則は上記法律の制定後2年内に制定されることになっていましたが,2年経過後の現在においてもまだ制定されていません。
しかしながら,通常は英語で行われる国際契約において,インドネシア語版を追加で作成するのは煩雑に過ぎ,コストもかかります。
そこで,多くの当事者は,「上記法律の施行細則が制定され,インドネシア語版が作成された場合でも,英語版が優先する」というような内容の条項を入れた英語版のみの契約を作成することで,現実的・実務的な観点から,上記法律に対処してきました(もっとも,保守的に考えて,インドネシア語版を作成することも場合によってはあり得ますが)。
ところが,今年6月,インドネシアの地方裁判所で,インドネシア当事者との契約を英語で作成した事案において,上記法律の定めを理由に,同契約が無効とされる判決がありました。このような判決が広く適用されると,インドネシア当事者とのすべての契約に厳格にインドネシア語版を用意しなければいけないことになりかねないため,本裁判の結果には悪評が高く,現在控訴中のようです。
控訴の結果の情報等が入りましたら,本コラムにおいて更新いたします。
2013年07月03日 コリア・レポート -IPBA年次総会-
IPBA(環太平洋法曹協会)の年次総会に出席するため,4月中旬に韓国のソウルへ出張して参りましたので,ご報告します(中山達樹)。
■ IPBAとは
IPBA(Inter-Pacific Bar Association)には,環太平洋地域のビジネスに関心を持つ弁護士が主に参加しています。同会は,世界中で1,700人程度の会員を有しており,毎年環太平洋地域で行われる年次総会には1,000人程度が出席し,法律情報の交換等を行っています。
私は今年で6回目の参加となりました。6回目の参加となると,会議でも何度も発言できたり,夜の会合でも周りを巻き込んで楽しんだりすることができるので,主体的に参加してより有意義な参加・交流ができてきた感じがします。
■ ソウル
漢江という大きな川がソウルを横切り,大規模マンションが林立したり,幅広の高速道路が走ったりしている街並みは,(さほど高くない)ビルの間を縫って所狭しと首都高が走る東京とはだいぶ違うと感じました。
日本から近いため大して寒暖の差がないだろうと高をくくっていましたが,だいぶ日本より冷え込みました。4月中旬だというのに,夜の外出時にはコートが欠かせないほどでした。
韓国は日本よりも国際化している感がありますが,(特に年配の)市井の人には,ほとんど英語が通じませんでした。空港からの公共バスでも英語は通じませんでした。英語が通じない点では日本とさほど大差ないのだと思いました。なお,公共交通機関の値段は,日本の半分かそれ以下かと思われるほど安かったです。
関税及び政治的・感情的な問題でしょうか,日本車はほとんど見かけませんでした。日本でも韓国車はほとんど見かけません。このように,国際的競争力のある日本車と韓国車が,互いの国(相手国)では見かけられないというのは非常に稀有なのではと改めて感じました。
■ ソウルの法律事務所
韓国でも最大手と謂われる事務所を訪問したところ,日本に留学したりして日本語を話せる韓国人弁護士が5人以上も対応してくれたのには,びっくりしました。日本の大手法律事務所にも,韓国語を話せる日本人弁護士はほとんどいないはずです。
韓国ではゴルフが盛んで,ある法律事務所では,クライアントとの接待やコミュニケーションとしてゴルフが重要であることから,ゴルフのハンデを下げるよう事務所から指令が出ていると聞きました。体育会系というか軍隊的というか,日本では(おそらく他国でも)考えられないと思いました。韓国の法律事務所では,このような組織的・トップダウン的な意思決定をする事務所が多いそうです。
■ JAPAN NIGHTの主催
IPBAの年次総会では恒例となっていますが,主に日本人弁護士を集めてJAPAN NIGHTと称する一夜のパーティを主催しました。100名を超える方にご参加いただき,大変盛り上がりました。来年以降も,引き続きJAPAN NIGHTを盛り上げて行きたいと思います。
2013年03月18日 フィリピン・レポート2 ~投資のメリット・デメリット,法制度~
【コラム】
<フィリピン投資のメリット・デメリット>
■ フィリピン投資のメリット
今回私がマニラに赴いたもう一つの目的は,日系企業の投資先としてのフィリピンの可能性とその問題点を探ることでした。フィリピンは人口が約1億人で英語を話す人も多く,外資規制は低く,各種優遇税制・法制度・インフラもある程度整っており,しかも日本に最も近いASEANの国です。世界最高レベルで極めて親日的な国民性というメリットもあります。
その他,カトリックに基づき中絶がない(ちなみに離婚もありません)ことなどから,今後何十年も「人口ボーナス」の影響を享受して,高い成長を維持することが見込まれています。家族を重視する国民性もあり,出生率は3.11という高数字を記録しています(ASEAN2位)。そのため,人口ピラミッドも,日本のような釣り鐘型ないし逆三角形ではなく,綺麗なピラミッド(富士山)型をしています。
さらに,地理的な優位性も挙げられます。東京から3.5時間で,他のアジア諸国へも同程度の時間で行くことができます。フィリピンは,すべての東南アジア諸国に4時間以内で行ける唯一の国であり,その意味で,「東南アジアの中心」にあると言えます。
また,大学進学率も高く(約3割),工学系の人材が毎年30万人程度輩出されています。さらに,報道規制がないため,自由な情報が入手できます。
最後に,フィリピンのGDPの4分の1は,フィリピン人海外出稼ぎ労働者(Overseas Filipino Worker, OFW)からの海外送金で支えられています。そのため,海外からの送金が為替の影響を受けないようにするため,現地通貨ペソが安定していると言われています。
このように,種々の面から「アジア最高の投資環境」にあると言えます。注目されていないので目立ちませんが,実際,昨年7−9月期のフィリピンのGDP成長率7.1%は,ASEANでトップを記録しています。HSBC(香港上海銀行)は,2050年にはフィリピンのGDPが東南アジアでナンバーワンになると予測しています。
しかしながら,上記のような多くのメリットがあるにもかかわらず,日本からの投資は,ミャンマーほどには熱が上がっていません。昨年,ベトナムとインドネシアと合わせて,ようやくVIP (Vietnam, Indonesia and Philippines)などと言われて注目されてきましたが,まだまだ情報は少なく,いわば投資の「穴場」といえます。諸条件を考えると,対ミャンマー投資よりも,対フィリピン投資の方が何倍,何十倍も有利に思えるにもかかわらず,です(ミャンマーは,JICAなどによるインフラ支援が整った数年後からが投資しやすいと言われています)。
なぜフィリピン投資はそのメリットに見合う注目を得ていないのか? その淵源を探るべく,多くのフィリピン人及び在比日本人知識人から情報収集して参りました。
■ フィリピンに対する悪印象
いろんな人に話を聞きましたが,結局,投資環境としてはむしろ素晴らしいにもかかわらず,フィリピンがさほど(というか全く)注目されていないのは,主に単なる「悪いイメージ・印象」が原因と思われます。1983年のアキノ氏暗殺,1986年の若王子マニラ三井物産支店長誘拐事件,フィリピンパブに嵌ってフィリピン女性の尻を追っかけてフィリピンで裏切られ人生を台無しにする日本人男性(フィリピンの日本大使館には,一日に1,2人,そのような困窮邦人が助けを求めて駆け込みます),小向美奈子さんらの逃避先,日本の暴力団と銃… こんなところでしょうか。
■ マスメディアの偏った報道
しかしながら,<フィリピンという国と文化>ですでに触れたとおり,少なくとも現在はフィリピンで生活していることによる危険を感じることはほとんどありません。他のいわゆる途上国と同程度ということができ,フィリピンだけが突出して危険であるとか治安が悪いということはありません。政権が安定しないとも言われますが,それでもクーデターにより一般市民に危険が及ぶことはありません。こう考えてみると,やはりマスコミのイメージ操作による偏見が一番大きいようです。
マスコミのイメージ操作と書きましたが,特に日本のマスコミがフィリピン投資に対して否定的な報道をしたりすることがあるわけではありません。むしろ,ベトナム,インドネシア,ミャンマーばかりを取り上げて,これらの国と同様かそれ以上の魅力を有しているフィリピンへの投資を肯定的に報じなかったマスコミ他のメディアの怠慢に,責任があるといえます。
たとえば,メディアは国際部,政治部,経済部ではなく,社会部の記者ばかりをフィリピンに送り込んでいます。そのために,フィリピンの社会面を飾るような(危険な)事件ばかりが報じられることになり,投資環境に優れているというプラスの経済面が報じられないのです。
また,1966年にアジア開発銀行の本部がマニラに置かれたことに象徴されるように,フィリピンは,かつてはASEANの雄でした。そのフィリピンが,かつては世界最貧国でしたが外資誘致に成功して発展したタイに大きく水を空けられたのは,投資環境としては大差なかったにもかかわらず,政府のプロモーション努力に差があったからです。
このように,魅力に伴う報道が日本で行われていないため,視察に訪れた日本人の多くが,実際にフィリピンに接して「180度印象が変わりました」と言うことがあります。
■ 貧弱な政治
もうひとつ,フィリピンの停滞の理由を挙げるとすれば,やはり政治力の弱さでしょう。マルコス政権後のアキノ政権ではピナツボ火山噴火等に遭い経済政策は停滞し,その後の軍出身ラモス大統領は健闘しましたが,その後の元俳優エストラーダ大統領及び元学者アロヨ大統領ともに,財閥系の政商に勝てず,フィリピンの宿痾である汚職を払拭できませんでした。
どの国でもパレートの法則のとおり一部の特権階級・エリートが多くの富を所有しているのは事実ですが,フィリピンではそれが特に顕著で,2%の財閥が国富の98%を所有しているなどと言われています。
中間層拡大による消費の拡大を狙う政策が,財閥系の既得権益を奪うことになりかねない中で,今後も政府主導による強力な経済政策の実施に期待がかかるところです。
■ 安定成長
フィリピンは,日本からの注目度が相対的に低いこともあり,ベトナムやインドネシアのように急激に成長したということはありません。しかしながら,このような低成長の方がむしろ良いという見方もあります。なぜなら,急成長に伴う種々の「歪み」が生じないからです。つまり,ベトナムやインドネシアのように急激に注目されると,実態に見合わない大きな期待が,種々のトラブルを引き起こすからです。ベトナムやインドネシアで頻発する労働争議や,需要に追いつかないインフラ供給などはその具体例です。
■ 労働環境
失業率は高く,7%。増大する人口が豊富な労働力を供給していますが,需要がそれに追いついていません。そのため失業率が1−2%であるタイなどに比べると,従業員の採用が容易です。フィリピン人海外出稼ぎ労働者(OFW)がGDPの多くを占めているのも,フィリピン人の英語力と適応性が勝っていることだけではなく,フィリピン国内の労働力の需要がまだ少ないことを示しています。
マニラの居酒屋でも店員が余っており,狭いフロアに数メートルおきに店員がオーダーをただ待って立っていたりします。
■ 魅力的な移住先
投資そのものとは異なりますが,定年退職者の移住先としてもフィリピンは魅力です。暑すぎない温暖な気候,物価が低いこと,英語が使えること,そして日本への帰国が楽であることなどがメリットです。退職者の移住先としてはここ何年もマレーシアがトップですが,マレーシアに勝るとも劣らない魅力をフィリピンは持っているといえます。
■ フィリピン投資のデメリット
このように,魅力に溢れるフィリピン投資ですが,あえてデメリットを挙げると,貧弱なサプライチェーンが挙げられます。のんびりした国民性から,第二次産業で有望な地場産業が育っていません。そのため,部品の調達をフィリピン国内でまかなうのではなく,海外から輸入することが多いです。
また,電力供給会社が財閥に独占されているため,電力コストが日本並みに高いこともデメリットの一つです。その他には,正直申しまして,大きなデメリットは見当たりません。なお,日本人学校の生徒が半分くらい日比のハーフで占められ,そのような生徒は日本語もおぼつかないことが多いため,日本人学校の教育レベルが低い,というフィリピン特有の教育事情もあります。
■ まとめ
以上述べたフィリピン投資のメリット・デメリットを箇条書きで列挙すると,以下のとおりとなります。
⑴ メリット
① 人口1億人の大きなマーケット
② 高出生率が支える将来的な発展性(人口ボーナス)
③ (分かりやすい)英語の通用性
④ 地理的な優位性(東南アジアの中心に位置)
⑤ 魅力的な投資優遇制度
⑥ ある程度整ったインフラ
⑦ IT 系などの優秀で安価な豊富な人材
⑧ 親日的・平和的な国民性のため労働争議が少ない
⑨ 安定したペソ
⑵ デメリット
① おっとりとした国民性ゆえ,物事の進行が遅い
② 不十分な国内2次産業・サプライチェーン
<フィリピンの法制度>
■ 外資規制は,基本的に非常にオープンです。⑴小売業で250万USドル超投資しなければいけないことと,⑵土地所有会社は60%以上をフィリピンから出資しなければいけない以外は,特筆すべき外資規制はありません。基本的に,100%外資で出資できます(もっとも,株主が5人必要となり,そのうち3人はフィリピンに居住していなければいけないという要件があるせいで,現実的には100%出資ではなく99.97%などになりますが)。
■ その他,取締役は株主でなければならないとか,取締役の過半数はフィリピンに居住していなければならないとか,取締役の他に,財務役・秘書役(ともにフィリピンの居住要件あり。秘書役はフィリピン人であることが必要)などの役職がある点で,日本と異なります。
もっとも,これらのフィリピンの居住要件は,他国と同様,法律事務所や会計事務所等から年間10〜20万円程度で名目的役員を選任することで対処可能です。ですから,居住要件自体が進出の足枷になるとは言えません。
■ 300年以上もスペインの支配下にあったので,フィリピンの法制度は基本的にシビルローと言えるようです。アメリカの支配にあったのでコモンローだと思われがちですが,判例の拘束性はさほど強くありません。
フィリピンの裁判制度は,解決まで時間がかかります。普通の事件は第一審で2年くらいで終わりますが,争点について第一審の途中でも上訴が認められているため,その間,第一審の審理が停止することで,2年以上の時間がかかったりします。アメリカ的な証拠開示の制度はあるものの,アメリカ的に広範には利用されていません。
■ なお,シンガポールやベトナムやミャンマーには日系の法律事務所が進出していますが,フィリピンにはまだ進出していません(フィリピンに駐在する日本人弁護士も,たとえいるとしてもほとんどいません)。理由としては,治安の悪さに対する偏見の他には,現地企業の担当者が英語で現地人弁護士とコミュニケーションできること(この点ではシンガポールやマレーシアと同様)が挙げられるようです。
以 上
2013年03月18日 フィリピン・レポート ~フィリピンの文化・社会~
IPBA(環太平洋法曹協会)のAPEC(アジア太平洋経済協力)委員会代表として,フィリピンのマニラに出張して参りました。フィリピン事情などをご報告します。
<IPBAのAPEC委員会>
■ APEC委員会とは,私が所属するIPBAの委員会の一つです。IPBAは,2年前に,APECと友好協定を結び,アジア太平洋地域の法律・経済の発展に向けて,相互の協力関係を築こうとしております。
今回は,APECのSmall and Medium Enterprises Working Group (SMEWG)の会議がマニラで開かれ,IPBA代表として招かれました。「中小企業の国際化が抱える問題とその解決策」というテーマで,①中小企業の情報・人材・資金不足,②知的財産権の保護,③紛争解決方法という問題について,それぞれ解決策を提示してきました。
各国政府(各Member Economy)の多くのAPEC代表使節から,IPBAに対する高い関心と興味を示してもらえました。昨夏のサンクトペテルブルクのSMEWGでもAPECからIPBAのAPEC委員会がゲストとして招かれましたが,昨夏よりも,相互協力関係に向けて,大きく前進しているという好感触を得ることができました。
■ 4月にソウルで行われるIPBAの年次大会でも,APEC委員会が行うセッションには,日本のみならず,タイ,インドネシア,韓国からスピーカーが参加し,アメリカ人弁護士が司会者を務めます。各国の協力を得て,IPBAとAPECがより強固な協力関係を築くことができ,その恩恵を多くの日系企業・投資家の方に還元したいと思っています。
<フィリピンという国とその文化>
■ 基本情報
人口はASEAN2位の約1億人で,早晩日本を抜くことが確実です。マニラ首都圏の人口は約1500万人です。面積は日本の8割。7109の島から成ります。
宗教はカトリックが8割。英語が公用語として通じます。一人当たりのGDP(2012年)は2232ドルで,インドネシア(3509ドル)とベトナム(1374ドル)の中間にあります。
■ 国民性
(1) フィリピンはとても親日的な国です。東南アジアで最も親日的と言われるインドネシアよりも親日的で,台湾を差し置いて世界で最も親日的な国であるというデータもあるようです。
走っている車の7割か8割が日本車です。日本車の割合が(日本より)多いインドネシアも非常に親日的ですから,日本車の占める割合と,その国が親日的である度合いは大きく比例すると考えられます。そう考えると,日本の自動車産業の方々には是非とも頑張ってもらいたいものです。なお,マニラでは,ジャカルタやバンコクほど渋滞は激しくありません。
(2) 国民性も,旧宗主国スペイン系の血でしょうか,ラテン系のノリの良さ・陽気さ・気さくさがあります。乗り合わせたタクシーの運転手が,「困ったらなんでも連絡しな」と言って,名前とメモを書いた紙を私に渡してくれたりしました。タイその他の国では,このような親切(悪意に取れば詐欺ないし誘拐未遂?)に出逢ったことはありません。フィリピン人のホスピタリティは,「微笑みの国」としてホスピタリティ溢れるタイ人を差し置いて,世界最高とも言われたりします。
⑶ フィリピン人の特徴として,平和的・友好的であるという点が挙げられるようです。「クーデターがあった」というニュースがあったとしても,実際には叛乱軍はわざと政府軍を傷つけないような攻撃(のふり)をしているということもあるようです。
そのため,ベトナム,インド,インドネシアやミャンマーなどで見られるような労働争議はほとんどありません。国民性として,お金をあまり求めず,現状に満足して幸せを享受する,という考えがあるようです。
⑷ また,過去に拘泥しない明るい国民性もあります。例えば,靴を3000足も所有していたとして有名になったマルコス大統領イメルダ夫人 は,ハワイでの亡命を終え,今はフィリピンの下院議員として闊歩しています。タイでタクシン元首相が未だ亡命していることとの違いを考えさせられます。
⑸ ただ,注意しなければならないのは,フィリピン人は,良かれ悪しかれ,のんびり屋であるということです。人を急かして何かをさせることがSin(宗教的な悪)だと考え,何かを急かされることを嫌います。そのためビジネスの世界では,納期をフィリピン人に守らせることに一苦労することがあります。
また,細かいことに拘泥する性質でないためか,精密機械の製造などの高度な技術を要する仕事では,フィリピン人に任せっきりにするのではなく,日本人がしっかり管理・監督する必要があります。
⑹ のんびり屋であることに通じますが,中国などと異なり,日系企業の技術や知的財産がフィリピン人に盗まれるというようなこともない そうです。中国では,中国人に技術を盗まれてお客まで奪われるということが往々にしてあり得ますが,そのような事態を危惧する必要も高くないというのは, 安心して投資できるメリットになります。
■ 民族
⑴ 民族は,データ的にはマレー系95%ですが,中華系の血が混ざっている人も多いので,中華系とマレー系のミックスという感じでしょうか。ほとんどタイ人と容貌は変わりません。農村部から来た人などは,混血が進んでいないせいと,栄養不足でしょう,日本人と比べても非常に背が低いです。
⑵ スペイン,日本,アメリカの支配を受けたという歴史からか,混血が進んでおり,シンガポールが中華系・マレー系・インド系で棲み分けというか共存している人種の混在(salad bowl)であるとすれば,まさに人種の坩堝(melting pot)という感じがしました。
■ 気候
⑴ 気候は,東南アジア諸国の一番北に位置するから当然ですが,思ったほど暑くありません。湿度がそれほど高くないせいでしょうか,バンコクやシンガポールよりだいぶ涼しく感じました。
⑵ サイクロン(台風)もありますが,洪水で製造業がダメージを受けることはありません。工業団地がやや高地にあり,水が停留することがないからです。
■ 治安
⑴ フィリピンといえば治安が悪い,というイメージが先行していますが,日本人が実際に感じる治安は悪くありません。単なる犯罪発生率とは異なる,「体感治安」は悪くないということです。都市部ではもちろんホテルを出て平気で外を歩くことができます。
⑵ 日本の暴力団がいる,と言われていますが,普通の日本人が普通に生活している限りでは,その向きの影響に怯えるということはありません。日本の大手商社に勤める私の友人が3年間マニラに滞在していますが,明らかにその筋と分かる人と出会ったことは一度もないそうです。
⑶ 普通のタクシーも危なくて乗れない,と思われています。しかし,空港やある程度高級なホテルに来るようなタクシーでは,警備員が車両番号をすべてチェックするため,何かあってもその番号を元にタクシー運転手を捕まえることができます。そのため,これが犯罪抑止効果になっており,むしろ他の国のタクシーより安全ということができるかもしれません。
⑷ 銃のある国ですが,日本人が普通に生活している限りでは,不安はありません。銃の危険に晒されるのは,お金か女性が絡んだ場合だけであり,無差別発砲や日本のような通り魔事件はないようです。そういう意味では日本より安全という言い方もできるかもしれません。
⑸ なお,日本人が決して行ってはいけない地域に,スラム街があります。私は4年前に行きましたが,車から絶対に出るなと言われました。スラム街の鼻を突くような強烈な匂いは未だに忘れられません。
ただ,駐在する日本人は運転手付きの車で決まったところにしか移動しませんから,日常生活の中でスラム街の怖さを感じることは全くありません(何年も駐在していても,スラム街に行ったことすらない日本人が多いです)。
■ 言語
⑴ 現地語タガログ語もありますが,公式の場では英語が公用語です。ビジネスの世界では英語のみが通用しますが,市井の人々はタガログ語で暮らしています。親から学ぶ母語も,階層等によって,タガログ語であったり,英語であったりします。
英語が使えるため,コールセンターなどのビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)がインド以上に発達し,IT・BPO産業の成長率は20%を記録しています。
⑵ タガログ語は,スペイン語の影響を多く受けています。例えば,タガログ語の「こんにちは」は「カムスタ(Kamusta)」ですが,これはスペイン語の「コモエスタ(Cómo estás)」に由来しています。
タガログ語の訛りがある英語をタングリッシュ(Tanglish)といいますが,これは日本人に最も理解しやすい英語といえます。なぜなら,例えば,中国語訛りのシンガポールのSinglishでは,日本語にはない中国語の発声が訛りとして入り込んでいるため聴き取りにくいのに対して,タガログ語はスペイン語と同様,日本語と同様の発音で済むため,その訛りがあっても日本人に聴き取りやすいからです。
⑶ なお,マレー系の特徴でしょうか,インドネシアで多く聞かれるように,アルファベットのv(ヴ)をf(フ)と発音するフィリピン人を見かけました。
⑷ 基本的に,日常生活で英語が通じるというのは日本人にとって大きなメリットです。同じように治安が悪いと思われているインドネシアとの対比では,メイドとの英語でのコミュニケーションが容易であるということもあり,日本人駐在員が単身赴任ではなく家族を連れて行く割合は,インドネシアより高いようです。インドネシアでは,メイドと英語でコミュニケーション取れないことを嫌い,駐在員の奥さんが駐在員について行かず,単身赴任するケースが多いです。
余談ですが,フィリピンに駐在する日本人の奥さんについて,「駐妻は三度泣く」と言われたりします。最初は(イメージの悪い)フィリピンへの駐在が決まったとき,二度目は(メイドの扱いに慣れていないため往々にして甘やかしてしまう)メイドの(窃盗などの)不祥事,最後は,快適だったフィリピン駐在が終わって日本に帰国が決まったとき,です。
このように,暮らしやすさと英語環境から,駐在員が日本に帰国しても,子どもの英語教育のため,奥さんと子どもがフィリピンに残るという「逆単身赴任」も行われています。
2013年02月17日 ライセンス・技術援助契約の主なチェックポイント
【コラム】
ライセンス・技術援助契約の主なチェックポイント
先日行われた日本電子回路工業会・中小企業基盤整備機構の法律セミナー『企業の海外事業戦略と法務』において講師としてお話した,ライセンス・技術援助契約書作成の注意点につき,要点をお伝えします。
1 ライセンスの内容
(1) まず,何をライセンスの対象とするかを決定します。例えば,登録された特許権のみなのか,その他ノウハウも含むかという点です。
また,対象技術が武器に使用されるおそれがある場合等は,外為法上,経済産業大臣の許可が必要となるので注意が必要です。
(2) 次に,ライセンスの内容として,独占的か非独占的かを決定します。
ただ,「独占的」といってもその内容は一義的に決まるわけではなく,ライセンシーが関連会社へサブライセンスすることを許諾するかなど,細かく決める必要があります。
また,専用実施権を設定すると,特許権者(ライセンサー)が特許権の自己実施をすることもできなくなる(特許法68条)ので注意が必要です。
2 ロイヤルティ
(1) ロイヤルティをどのように定めるかは,ライセンス契約の中で最も重要です。
具体的には,①頭金その他の定額ロイヤルティか,②ランニング・ロイヤルティの両方ないしいずれかを決定することになります。
(2) ランニング・ロイヤルティを定める場合,基準額をどうするかを明確に細かく規定します。販売価格から運賃・保険料・梱包費などの経費を控除した正味(純)販売価格とすることが多いですが,何を控除するかを明確に規定するようにしてください。
(3) 特に,独占的なライセンスを与えた場合は,ミニマム・ロイヤルティを定めて,ライセンサーは常にそのミニマム・ロイヤルティをライセンシーから入手できるように定めておくことが一般です。
3 知的財産権
(1) ライセンス契約では,知的財産権の侵害に対する措置を定めておくことが重要です。
具体的には,①ライセンサーが,対象技術が第三者の知的財産権を侵害していないことの保証をしたり,②第三者からの知的財産権侵害クレームに対し,だれが,だれの費用負担で,どのように対応するかを明記したりします。
(2) また,対象技術の改良や新たな発明を行った場合の知的財産権について定めておくことが必要です。
具体的には,①それらの権利が,当事者のいずれに帰属するか,それとも共有となるのか,また,②権利の帰属及び使用について,有償とするのか,無償とするのかです。
(3) 独占禁止法との関係については,知的財産権の行使と認められる行為には独禁法は適用されないとされていますが(独禁法21条),より具体的には,公正取引委員会のガイドラインをご参照下さい。
4 技術指導
技術援助契約では,技術援助のためにライセンサーから技術指導者をライセンシーに送ったりすることがあります。この場合に,どのような技術者を,どの程度の期間・頻度で,どちらの費用負担で送り込むかを定めますが,さらに細かく以下の費用もいずれが負担するかをあらかじめ定めておくことが望ましいです。
① 交通費・食費・往復旅費(航空券はビジネス/エコノミーか)
② 派遣される技術指導者の人件費(月給)
③ 宿泊施設(4つ星相当のホテル等)
④ 空港への送迎費用
⑤ 通訳・翻訳費用
⑥ ビザ・労働許可等の取得費用
5 情報提供義務
フランチャイズ契約と同様,ランニング・ロイヤルティの金額を正確に確認するため,ライセンサーがライセンシーの財務情報を入手できるようにしておくことが必要となります。
6 秘密保持義務
特にこの種の契約では,ライセンシー側に厳密な秘密保持義務を負わせることが重要です。
秘密保持条項の留意点としては,①第三者(例えば下請業者)に開示する場合は,その第三者に対しても同様の秘密保持義務を負わせているか,②契約終了後も(少なくとも一定期間)秘密保持義務が存続するか,という点が挙げられます。
以上
2013年02月16日 販売店・代理店・フランチャイズ契約の主なチェックポイント
【コラム】
販売店・代理店・フランチャイズ契約の主なチェックポイント
先日行われた日本電子回路工業会・中小企業基盤整備機構の法律セミナー『企業の海外事業戦略と法務』において講師としてお話した,販売店・代理店・フランチャイズ契約書作成における,主な注意点をお伝えします。
1 販売店契約(Distributorship Agreement)と代理店契約(Agency Agreement)の違い
(1) 「販売代理店」の意味?
しばしば「販売代理店」という言葉が使われますが,まず,この法的な意味をしっかり把握する必要があります。「販売店」と「代理店」では,それらの行う行為の法的効果が属する主体が以下のように異なります。
すなわち,まず「販売店」とは,販売店が,売主と買主の間に入って,販売店自身が売買契約の当事者となる形(売主-販売店間と販売店-買主間に2つの売買契約が成立する形)をとる場合をいいます。この場合,通常は販売店は手数料(コミッション)を取ることで利益を上げるのではなく,売主からの購入価格と買主への販売価格の差額が利益になります。
一方,「代理店」とは,代理店自身が売買契約の当事者とはならず,代理店の行為の効果を売主に帰属させ,売買契約は売主-買主間の1つのみが成立する場合をいいます。そしてこの場合には,代理店は手数料(コミッション)を得ることで利益を上げます。
しかしながら,多くの実務では上記両者の違いをあまり意識せずに使っています。公正取引委員会の流通・取引ガイドラインも,販売店と代理店を区別せずに「代理店」という用語を使用しています。
契約書作成において,「販売店」「代理店」という言葉が絶対で,その言葉によって法律効果が決せられるというわけでは必ずしもありません。ただ,当事者間でどのような形態の取引をするかについては,しっかり事前に明らかにしておく必要があります。
(2) PE(Permanent Establishment)の問題
上記区別は,教科書的な,販売店ないし代理店の行為の法的効果がだれに帰属するかという問題ですが,ここに国際課税の問題が絡むため複雑になることがあります。すなわち,一般的には,代理店はPE(恒久的施設)に該当するとして,その代理店がある国の事業所得が課税対象となります(OECDモデル条約及び日米租税条約5条5項,同7条,法人税法141条3号)。
ところが,いわゆる代理店が問屋(商法551条)や仲立人(同543条)のような「独立代理人」と評価されれば,売主は「独立代理人」を置いた国での課税を避けることができます(法人税法施行令186条,基本通達20-2-5)。この「独立代理人」に該当させるという課税回避目的のため,「代理店」という形式をとらず,問屋の形式をとる契約を締結することもあります。
2 フランチャイズ契約の性質
フランチャイズ契約は,販売・代理店契約とライセンス契約の性質を併せ持っています。フランチャイジーの売上の一定割合をフランチャイザーに納めるロイヤルティの定めと,ライセンス契約にあるような商標権の使用許可の定めが,フランチャイズ契約の根幹をなします。
3 注意すべき法律
(1) 販売店・代理店・フランチャイズ契約では,垂直的な競争制限(例えば,再販売価格の維持や優越的地位の濫用)が独占禁止法に触れるおそれがあります。詳しくは公正取引委員会のガイドラインを参照してください(流通・取引ガイドライン,フランチャイズ・ガイドライン)。
(2) フランチャイズ契約では,中小小売商業振興法に基づき,フランチャイザーが,フランチャイジーに対し,事業内容等の法定の情報を開示することを要求されます。
(3) なお,EU加盟国には代理店保護法があり,これが強行法規的に適用されることがあるので,EU加盟国との取引の際には別途注意が必要です。
4 排他性・競業避止義務
(1) 独占的か非独占的か
この種の契約で最も重要なのが,販売店・代理店・フランチャイジーに,ある地域の「独占的」な権利(販売権やフランチャイズ権)を与えるか否かです。また,「独占的」といっても,その内容を明確にしておく必要があります。
例えば,以下の点を前もって定めておくことが望ましいです。
ア 売主やフランチャイザー自身が販売地域へ進出することを許容するかどうかイ 販売店・代理店・フランチャイジーが,副代理店(サブフランチャイジー)を選任することを許容するかどうか
(2) 競業避止義務
売主やフランチャイザーからすれば,販売・代理店やフランチャイジーが,競合品を販売できるというのでは,販売・フランチャイズ権を与えた効果が減殺されかねません。そこで,販売・代理店やフランチャイジーが競合品を販売することを禁じる定めを設けておく必要があります。
5 最低購入数量・ロイヤルティの設定
特に独占的な契約を結ぶ場合,販売・代理店・フランチャイジーに対して,最低数量の購入義務や最低ロイヤルティの支払義務を課すことがあります。この場合は,これらの設定数値を達成できなかった場合の対応策まで検討しておく必要があります。
具体的には,主に
① 単なる努力目標として特に対応策を予定しない
② 非独占的契約へ変更する
③ 契約を解除する
などが考えられます。
6 知的財産権や製造物責任
この種の契約では,商標ライセンスを伴うことが一般です。また,商品に対する製造物責任をだれがどの程度負うのかを定めておくことも望ましいです。
例えば,売主(フランチャイザー)の立場なら,なるべく知的財産権侵害の責任や製造物責任を負わないようにします。具体的には,他者の部品・指示・仕様に基づいて製品を製造した場合や,損害発生につき販売・代理店やフランチャイジーに責任がある場合は,売主(フランチャイザー)が責任を免れる定めを置くことをお奨めします。
さらに,売主(フランチャイザー)や販売・代理店(フランチャイジー)の損害賠償義務の限定化も重要です。具体的には,売主(フランチャイザー)が損害賠償義務を負う場合であっても,間接損害や懲罰的損害までは負わないとか,販売・代理店(フランチャイジー)が損害賠償義務を負う場合であっても,目的物の価格の限度までしか負わないなどの定めがあります。
7 情報提供義務
特にフランチャイズ契約では,フランチャイザーが確実にロイヤルティを入手するために,フランチャイジーの正確な財務情報を入手できるようにしておくことが重要です。
8 契約終了事由
これらの契約は,一時的な契約ではなく,長期間継続することが予定されている契約なので,一般的に,ある程度の期間を設けないと解除することは困難です。そのため,何が契約の解消事由となるか,解除するためには何か月前からの通知が必要か,などをあらかじめ定めておくことになります。
また,契約関係が終了後に,残存した在庫や商標が表示された物品の処理(例えば,これらの返還義務や廃棄義務をどちらの費用で負担するか)をどうするかなどを決定しておくことも重要です。
以上
2013年02月11日 国際売買契約の主なチェックポイント
【コラム】
国際売買契約の主なチェックポイント
先日行われた日本電子回路工業会・中小企業基盤整備機構の法律セミナー『企業の海外事業戦略と法務』において講師としてお話した,国際売買取引における契約書作成の注意点につき,要点をお伝えします。
1 引渡条件・危険負担
FOB,CIFなどを定めるインコタームズ(Incoterms)2010に従うとするのがよくある契約条件です。
2 所有権の移転時期
所有権の移転時期についてはインコタームズ2010に定めはないので,例えば代金完済まで売主が所有権を留保する必要がある場合などは,その旨を明確に定めておく必要があります。
3 瑕疵担保(保証)責任
売買契約で最も大事なのが,売主の保証責任です。契約の目的に従った目的物の引渡義務をどれくらい厳格に定め,この義務の履行をどのように確認し,この義務違反に対してどのような救済策を定めるか,が非常に重要です。
具体的には,日本の民法570条や商法526条の瑕疵担保責任やウィーン国際売買条約(CISG,後述)が適用されるのか(例えば,隠れたる瑕疵の検査通知期間はどれくらいが適当か?など)を吟味することが重要です。
また,買主の立場で契約を締結するときは,目的物が仕様(specifications)に合致すること,商品性(merchantability)や特定目的への適合性を有すること,知的財産権の侵害がないこと,までを売主に保証させることが望ましいです。
さらに,売主が明示的だけではない黙示的な保証責任を負うのか(アメリカ統一商事法典〔UCC〕では負うとされる),保証期間はどれくらいか,なども検討対象になります。
4 支払方法
売主の場合,支払を確保するためになるべく早く支払わせるという観点から,逆に,買主の場合,確実な目的物の引渡を確保するためになるべく遅く支払うという観点から,支払時期を定めます。具体的には,前払いなのか,COD(Cash on delivery=商品と引換え)なのか,検収後の支払なのか,という点です。
さらに,支払手段として,電信送金なのか荷為替信用状なのか,また,支払手数料をいずれが負担するかという点もあらかじめ決めておく方がよいでしょう。
5 救済手段
売主が契約に沿った目的物を給付しない場合に,買主がどのような救済手段をとることができるかをあらかじめ考えておきましょう。
具体的には,瑕疵のない代わりの目的物を交付する義務や目的物の修理義務があるか,損害賠償額の範囲はどれくらいか,などです。なお,中国やタイの製造物責任法には,損害の2倍までの懲罰的損害賠償義務があるので注意が必要です。
<参考 ウィーン売買条約(CISG)>
正式名称は「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)です。現在,世界の78か国が加盟しており,日本に対しては平成21(2009)年8月から発効しています。
(1) 適用範囲
ア いわゆる国際売買契約,つまり,「営業所が異なる国に所在する当事者間の物品売買」に適用されます。
ただ,消費者売買(家庭用に購入された物品の売買)などは除かれます。
イ ①売買契約の当事者双方がCISGの締結国である場合や,②CISGの締結国の法律が準拠法となる場合に適用されます。
なお,準拠法の定めがない場合は,輸出国が売買契約の最密接関係地と推定されることから(法の適用に関する通則法8条2項),輸出国が日本である場合はCISGが適用されると考えられます。
ウ CISGは,売買契約の成立と契約から生じる権利義務につき規定しており,契約の有効性や所有権の移転については規定していません(CISG4条)。
(2) 締結国
締結国78か国中,いわゆる先進国で締結していないのはイギリスです。アジアでは,中国,韓国,シンガポール,モンゴルが加盟しています。締結国はこちら(国連のサイト)で確認できます。
(3) 日本法との違い
主に以下の点で,日本法と異なります。
ア 契約の成立に関して
① 日本の民法は発信主義を取り,承諾の発信時に契約が成立しますが(民法526条),CISGでは到達時に成立します(CISG 18条2項)。
② 日本の民法では申込みは原則として撤回不能ですが(民法521条,524条),CISGでは原則として撤回可能です(CISG16条1項)。
③ 日本の民法では申込みと承諾の内容が完全に一致することが原則的に要求されますが,CISGでは,申込みと承諾の内容が完全に一致しなくても契約が成立するとされます(CISG19条2項)。
④ 日本の商人間では「遅滞のない」期間内に諾否通知義務がありますが(商法509条),CISGには諾否通知義務はありません(CISG18条1項)。
イ 瑕疵担保責任
日本の民法のように隠れた瑕疵の場合の瑕疵担保責任の特別規定はなく,売主の一般的な目的物引渡義務(CISG35条)の問題として扱われます。
ウ 契約解除
日本の民法とは異なり,契約の解除ができる場合が,重大な契約違反に限定されています(CISG25条,49条,64条)。
エ 過失責任主義の否定
日本の民法とは異なり,当事者に過失がなくても,損害賠償責任が発生することになっています(CISG45条1項,61条)。
オ その他
日本の民法とは異なり,履行期到来前でも,契約違反が予想される場合に履行の停止や契約解除ができるなど,予防的な措置が認められています(CISG71,72条)。
また,日本では明文化されていない損害軽減義務も,CISGでは明文化されています(CISG77条)。
(4) 実務的対応
CISGの適用が実務的に定着しているとはまだいえませんし,CISGは任意規定であることから,「CISGの適用を排除する」と契約書に明記することが多いです。
逆に,このような排除規定を置かない場合は,契約当事者双方がCISG締結国に所在していたり,契約の準拠法が日本法となったりするときには,CISGが適用されてしまう可能性があるため注意が必要です。
以上
2013年02月10日 合弁(株主間)契約の主なチェックポイント
【コラム】
合弁(株主間)契約の主なチェックポイント
先日行われた日本電子回路工業会・中小企業基盤整備機構の法律セミナー『企業の海外事業戦略と法務』において,海外取引における契約書作成の注意点につき,講師としてお話させていただきました。
そこでお話した,国際取引でよく使われる①合弁契約(株主間契約),②売買契約,③販売店・代理店・フランチャイズ契約,④ライセンス・技術援助契約につき,主な注意点を4回に分けてお伝えします。まず第1回は,①合弁(株主間)契約のチェックポイントをご説明します。
1 定義
合弁契約書で使用される文言を定義することが多いですが,自分以外の第三者が,数十年後にも明確に一義的に分かるような用語の使用を心掛けましょう。例えば,Affiliate(関連会社)と Subsidiary(子会社)を明確に使い分けたり,「関連会社」に孫会社や兄弟会社を含めるかなどを吟味しておくことも必要となったりします。「子会社」についても定義が必要で,ある会社の「支配(Control)を受ける」とはどのような場合を指すのか,までを具体的に想定しておくことも必要となったりします。
2 許認可
現地で当局から会社設立・営業の許認可を受けることについては,海外進出する場合,日本側当事者には如何ともし難いものが多いです。そのため,許認可が取れずに合弁の目的が達成できない場合には,現地パートナーに責任を負わせる条項を入れておくことが有用です。
3 定款との関係
定款と合弁契約の双方に,合弁会社の運営につき同内容の条項を入れることがあります。合弁契約の存在意義は,相手方当事者が契約不履行となった際に,相手方に損害賠償請求をすることにあると考えてよいでしょう。なお,定款に当事者の固有名詞を使用すると,固有名詞が変更された場合に定款変更の手続が理論的には必要となります。
4 当事者の役割
合弁契約に,当事者(株主)の果たす役割を記載することがあります。抽象的な役割を記載するだけで,この条項自体が相手方に対する損害賠償の根拠になることは少ないと思います。ただ,①この条項の内容を詰める合弁契約前の交渉時に,その合弁事業に対する相手方の意図や背景が明確になる(そのため,どのような場合に合弁の解消があり得るかという想像がしやすくなる)というメリットや,②将来の紛争時に,合弁当初の当事者の意思の確認ができたり,紛争解釈の指針となったりし得るというメリットもあります。
5 ファイナンス(出資・融資・保証義務)
合弁事業における資金調達をどのように決定するかを合弁契約であらかじめ規定します。多くは,出資割合の比率に応じて当事者が応分に負担するというものです。
具体的には,以下のようなチェックポイントがあります。
① 設立時:現物出資を許すのか,それとも現金による出資のみなのか
② 追加出資(増資)の際:新株引受権の規定(通常は出資比率に応じた分 配だが,一方当事者が株式引受を拒否した場合に,どのような条件で第三者割当をするか)
③ 金融機関からの融資,保証,利益配当・残余財産分配:それぞれ,出資比率に応じることでよいか
6 機関構成
(1) MD(Managing Director)という役職はない?
東南アジアでは,現地社長をMDと呼称することが多いですが,これは多くの場合,法律上の役職ではありません。MDという呼称を実際用いる場合も,その権限が日本の代表取締役とどのように違うのか,現地の法律を確認する必要があります。例えば,タイでは重要書類のサイン権者のことをAuthorized Directorといいますが,この役職をだれにするのかの決定が,MDの決定より重要です。
(2) 取締役会と株主総会の区別
日本のように取締役会と株主総会が峻別されていない国もあるので注意が必要です。中国の董事会やベトナムの有限会社の社員総会は,日本の株主総会と取締役会を兼ねるような役割を担っています。
(3) 株主総会特別決議要件
外国では,株主総会の特別決議要件が,日本とは違う場合が多いことに注意が必要です。タイ,シンガポール,インド,マレーシア,ベトナム,ミャンマー等では,日本のように株主総会の出席株主の議決権の「3分の2」以上ではなく,「4分の3」以上となっています。インドネシアでは3分の2以上と4分の3以上が並存しています。ですから,このような国では,日本のように「70%株式を保有していれば特別決議も支配できて安全」というわけではありません。
ちなみに,ベトナムは普通決議要件も,過半数ではなく3分の2以上であり,この点でも日本と異なっています。
(4)「監査役」の各国における違い
余り知られていませんが,日本の「監査役」(Audit and Supervisory Board Member)は世界的に見てもむしろ特殊な機関といえるでしょう。海外では監査役は必要的機関ではなく,単にAuditorといえば,タイのように(会社外部の)公認会計士を指すことが多いです。
なお,インドネシアのコミサリス(Commissioner)は日本の監査役に近い役割を担っていますが,取締役の業務を一時停止できるなど,日本の監査役以上に強力な権限を有していますので,注意が必要です。
7 会社のガバナンス
会社運営につき相手方と争いになる場合に備えて,どこまでを代表取締役個人が決定でき,何を取締役会決議事項とし,何を株主総会決議事項とし,何を株主総会特別決議事項とするかを,別紙に列挙するなどして,できる限り具体的に規定しておく場合が多いです。
例えば,1,000万円以上の取引・借入れは取締役会決議事項として,1億円以上の取引・借入れを株主総会決議事項とする,などです。
8 デッドロック
(1) デッドロック発生事由
合弁当事者の意思が合致しないために会社の意思決定ができない膠着状態をデッドロック(Deadlock)といい,50対50で合弁事業を行う場合や,少数株主が拒否権を持っている場合に主に発生します。日本側が少数株主である場合は,多数株主の言いなりにならないため,一方,日本側が多数株主である場合は,少数株主が勝手にデッドロックを主張して容易に合弁解消をさせないため,何が「デッドロック」となるか,その発生事由を慎重に決定する必要があります。
(2) デッドロック解決方法
デッドロックの解決方法としては,主に以下の3つが挙げられます。
① 協議
② 一方当事者の株式の購入(Call Option)・譲渡(Put Option),または第三者への譲渡(First Refusal Right等)
③ 解散
上記の中でも特に重要なのは②の株式譲渡であり,株式の譲渡価格をどのように決定するかまでを詳細に規定しておくことが望ましいです。
9 株式譲渡禁止
合弁会社では,第三者に対する株式譲渡に制限を設けることが一般であり,その制限の内容まで具体的に合弁契約で定めておくことが重要です。特に,一方当事者が第三者に株式譲渡をしようとする場合に,他方当事者に以下のような権利を与えて,合弁事業の存続または事業からの撤退を容易にするような手はずをあらかじめ整えておくことが大事です。多くの合弁契約では①の先買権を定めています。
① First Refusal Right (先買権)
② Tag Along Right (売却参加権・共同売付請求権)
③ Drag Along Right (強制売却権・一括売渡請求権)
また,デッドロックの解消の場合と同様,ここでも譲渡株式の株価の算定方法を具体的に定めておくことが多いです。
10 競業避止義務
合弁会社の売上を確保するため,合弁パートナーである相手方当事者やその関連会社が,合弁会社と競業する事業を行うことを禁止しておくことが多いです。この場合に「関連会社」の定義が重要になったりします。
ただ,競業避止義務を設定する際には,各国の競争法・独占禁止法との関係に注意する必要があります。また,中国の独禁法は,(中国に子会社を有する親会社が他国に進出する際に)中国のみならず外国でも問題になることがありますので,注意が必要です。
11 合弁解消方法
(1) 解消事由
何を合弁の解消事由とするかを,あらかじめ具体的に定めた方がいいでしょう。よくある合弁解消事由の例としては,以下が挙げられます。
① 合弁会社の経済的事由(例えば,3期連続の赤字計上,資本金の一定割合の損失計上など)
② 合弁契約の重要な違反が一定日数以上治癒しない場合
③ 両当事者の合意
④ 合弁の目的達成不能が明らかになったとき
⑤ デッドロック状態の解消ができなかったとき
⑥ Change of Control (支配株主の変動)
⑦ 契約期間(例えば30年)満了
(2) 解消方法
上記の合弁解消事由が発生した場合の合弁の解消方法も,具体的に定めておく方が望ましいです。代表的な解消事由は以下が挙げられます。
① 相手方当事者への株式譲渡または相手方当事者の株式購入(Put/Call Optionなど)
② 第三者への株式譲渡
③ 解散
以上